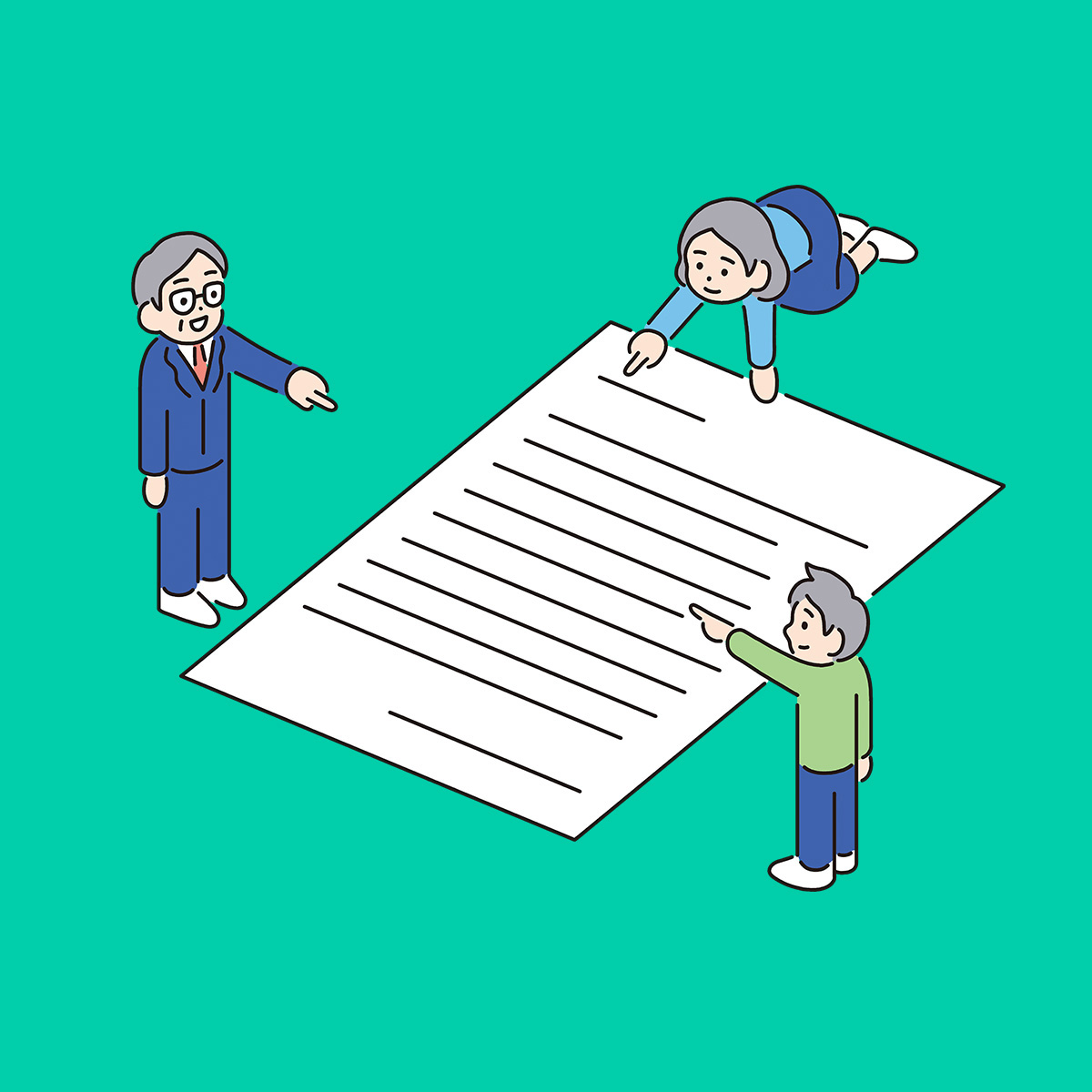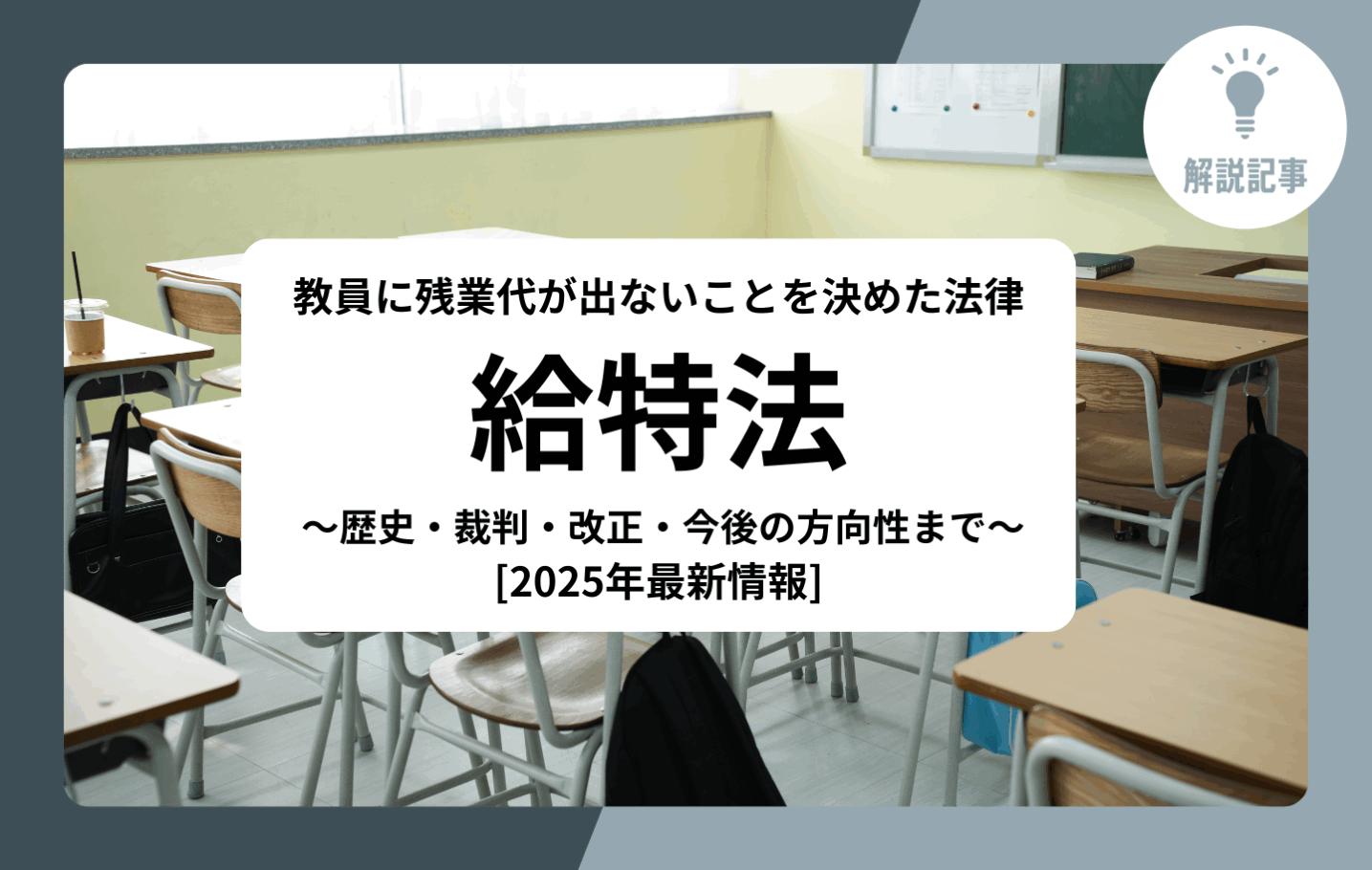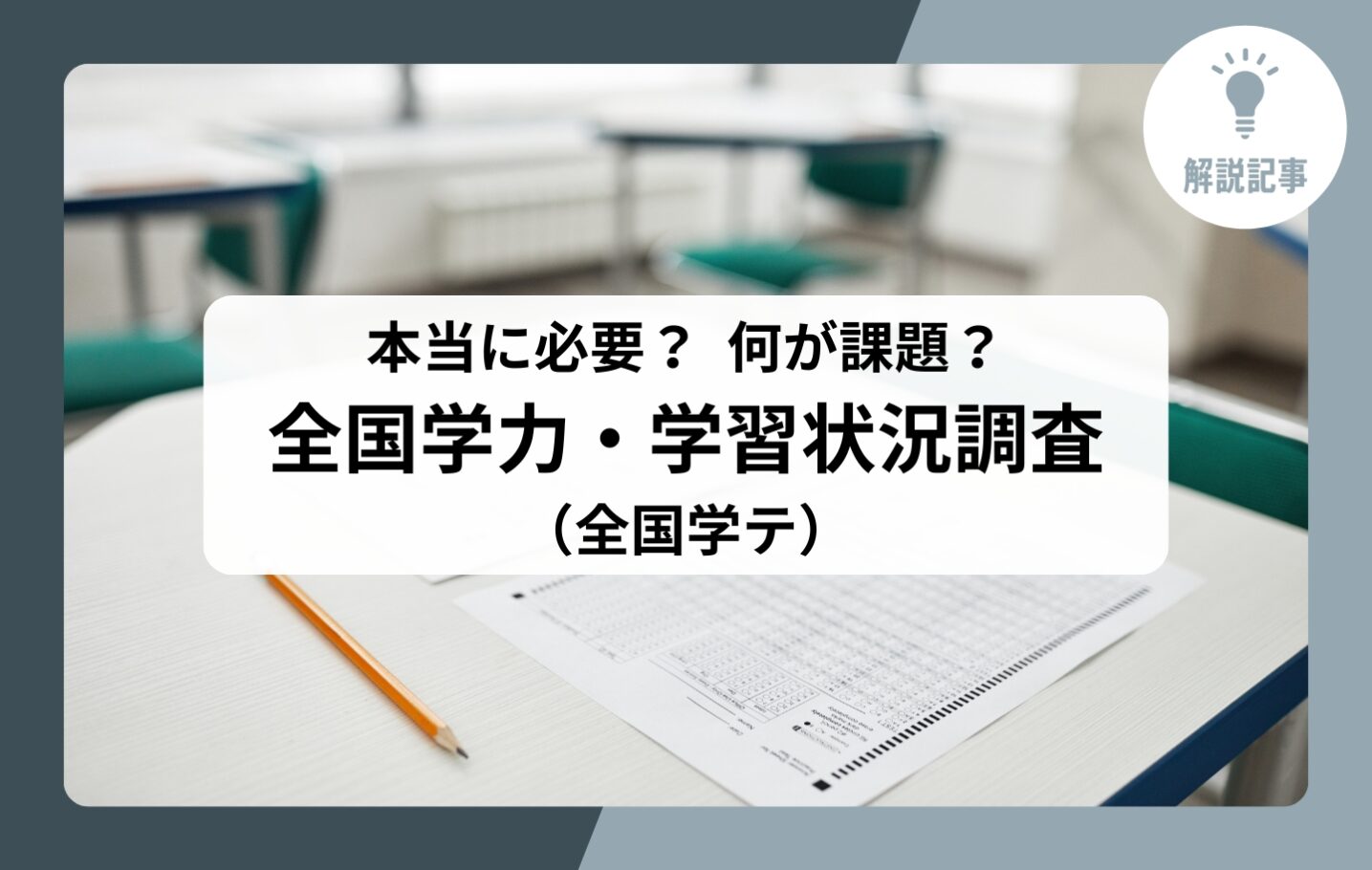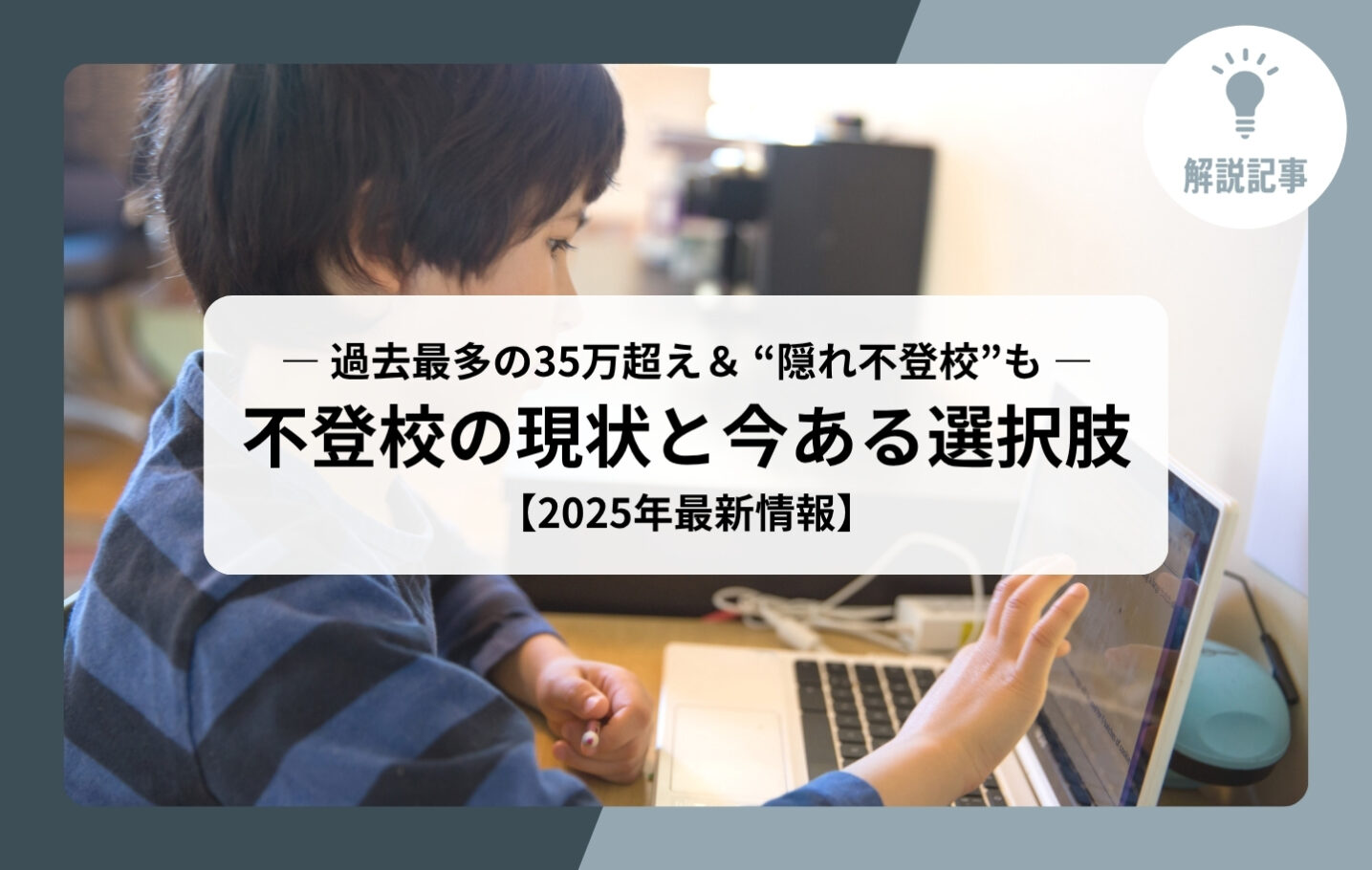
【解説記事】[2025年最新情報]文科省調査で過去最多の35万超え。不登校児童生徒の現状と、今ある支援を紹介
不登校が認知されるようになり長く経ちました。しかし、今なお不登校の生徒は増えています。さらに、不登校の定義には含まれていませんが、その傾向にある子どもも多くいるとの調査もあります。
これに対して、一概に学校復帰だけを目指すものでない、多様な不登校支援のあり方がされつつあります。今、改めて不登校の現在の課題や実践などについて説明します。
関連記事:【これからの学校】子どもたちの“SOS”への向き合い方を立場を超えて語り合う
文科省の不登校の定義
不登校とはどのような状態を指すのでしょうか。
文部科学省(文科省)は、不登校を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。
昭和時代では「学校ぎらい」を理由とした欠席を範囲としていましたが、平成10年以降「不登校」という言葉に置き換えられ、「学校に通いたいけど通えない」子どもたちまでを含めるものとなりました。
参考「不登校の現状に関する認識 – 文科省」(文科省,2009年以前公開,2022年10月31日参照)より
参考「生徒指導資料第1集(改訂版)第3章 不登校」(国立教育政策研究所 生徒指導研究センター,2009年3月公開,2022年10月31日参照)より
不登校の現状
2024年度の文科省の調査では、小・中学校における不登校児童生徒数は過去最多の35万3970人と発表されました。前年度からは7,488人、2年前に比べると5万4922人の増加となります。不登校の定義が現在と同じになった平成10年の時点では、小・中学校を合わせて12万7692人でしたが、ここ10年ほどは増加の一途を辿っています。
では、実際の学校の中には、どれくらい不登校の子どもがいるのでしょうか。
小学校では13万7704人で、全体の2.3%の児童が不登校にあたります。1学年3クラスの学校では学年に2人以上いる計算となります。中学校では21万6266人で全体の6.8%です。30人以上のクラスでは1クラスに2人はいる計算となり、学校・教員は必ず考えなければいけない問題であると言えるでしょう。
多くの子どもが直面する不登校について、より詳しく掘り下げていきます。
参考「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文科省,2024年10月31日公開,2025年5月15日参照)より
「隠れ不登校」「不登校傾向」の子どもたちはどれくらいいる?
定義上当てはまらないけれど同様の苦しさを抱える子どもたちもいます。「隠れ不登校」「不登校傾向」などと言われる子どもたちです。
認定NPO法人カタリバによる2023年の調査では、「部分/教室外登校(保健室登校や一部の授業のみに参加する生徒など)」「仮面登校(ほぼ毎日、学校に通いたくないと思っている生徒)」に注目しました。教室に入らなかったり、登校していても遅刻や早退が多かったり、内心では「行きたくない」と感じていたりする中学生が推計41万人いるとしています。これは中学生の約5人に1人が「不登校」または「不登校傾向」に該当することを示しています。
参考「不登校に関する子どもと保護者向けの実態調査」(認定NPO法人カタリバ,2023年12月9日公開,2025年5月15日参照)より
また、実質的には不登校の子どもが教員や学校の判断によって「病気による長期欠席者(長期病欠)」とカウントされている事例も報道されています。
記事によると、行き渋る子どもが頭痛や腹痛を訴える場合、病欠とするか不登校による欠席と捉えるかは、「保護者や担任の判断」(中日新聞)とされ、「不登校かどうかの判断が学校ごとに異なる可能性はあり得る」(熊本市教育委員会,熊本日日新聞による)とも述べられています。
引用「不登校最多、出欠判断の基準はあいまい 学びの場多様化、実態反映せず」(中日新聞,2022年10月28日公開,2025年5月20日参照)より
引用「不登校のはずの娘が「長期病欠」扱い 明確な基準なく、学校が「総合的に判断」 数字に表れない〝隠れ不登校〟も存在か」(熊本日日新聞,2022年12月21日公開,2025年5月20日参照)より
多くの場合、「病気による長期欠席者」という表現からイメージされるのは長期間入院をしている児童生徒が中心かと考えられますが、2013年度の文科省調査では小・中学校における長期入院児童生徒数は全国で2,769人とされている一方で、それから2年後の2015年度の「病気による長期欠席者」は4万1064人と報告されており、約15倍の乖離が見られます(※「病気による長期欠席者」の人数は2015年度調査から公表開始)。
また、近年のデータに限っても、「病気による長期欠席者」は2021年度から2024年度の3年間で5万人以上増加しており、純粋な“病気のみによる長期欠席”としては不自然な推移が見られます。上記の報道等と併せて考えると、本来「不登校」とカウントされるべき子どもが「病気による長期欠席」と報告されていることが示唆されていると言えるでしょう。
参考「長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査の結果(概要)」(文科省,2025年5月20日参照)より
不登校の理由
なぜこれだけ多くの子どもが不登校、またはその傾向になるのでしょうか。
学校側から見た要因
文科省による2024年度の学校に対する調査では、「長期欠席者の状況」で「不登校」と回答した不登校児童生徒全員につき、教職員が当てはまるものをすべて回答する形式をとっています。
同調査によると、小学校・中学校共通して、「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった」の選択肢の回答割合が最も多く、いずれも30%を超えています。ついで「生活リズムの不調に関する相談があった」、「不安・抑うつの相談があった」が25%ほどと多く、「学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた」(15%)と続きました。
学校から見た不登校の要因には、校種を問わず一定の傾向があることがわかりますが、校種や学年によってその実態は様々です。例えば中学校では、進学に伴う学習や生活の変化によっていじめや不登校が増加する「中1ギャップ」が広く認知されています。文科省は小学校高学年教科担任制を導入するなどの対策を打ちましたが、国立教育政策研究所は安易な表現に振り回されず、児童生徒の課題を見据える必要性を指摘しており、中1ギャップという問題の捉え方に注意を促しています。また、高等学校では、2000年以降減少傾向ではありますが中退というケースもあります。留年や通信制への転校など、おかれる状況も多種多様で、実態把握の難しさがあります。
参考「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文科省,2024年10月31日公開,2025年5月15日参照)より
参考「「中1ギャップ」の真実」(文科省,2014年4月公開,2025年5月20日参照)より
参考「高校生にみる不登校傾向に関する研究 : 意識調査を通して」(山下みどり, 清原浩,鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要,2004)より
不登校児童生徒本人や家庭から見た要因
2024年3月には、公益社団法人 子どもの発達科学研究所から文部科学省委託の「不登校の要因分析に関する調査研究 報告書」が発表されました。
不登校のきっかけ要因を学校、家庭、本人それぞれを対象に調査した同資料によると、「学業の不振」、「宿題の提出」については、三者の回答割合が比較的近い値となりました。一方で、「いじめ被害」、「教職員への反抗・反発」、「教職員からの叱責」等については、教師の回答がわずか2~4%であるにもかかわらず、児童生徒・保護者は20~40%が回答するなど、割合に大きな差がみられました。
また、「体調不良」、「不安・抑うつ」、「居眠り、朝起きられない、夜眠れない」といった心身不調・生活リズム不調についても、児童生徒や保護者の60~80%が回答しているのに対して、教師の回答割合はいずれも20%未満と、低く留まりました。
不登校については様々なケースがあり、また一つのケースでも複合的な要因があることも多いため、唯一の原因を特定することはできません。教職員に対する調査だけでは視点に偏りが生じうるため、現場で児童生徒の個別の事例に向き合っていく必要がある一方で、不登校児童生徒本人や家庭の実態把握が今後ますます重要になりそうです。
参考「文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究」(公益社団法人 子どもの発達科学研究所,2024年3月公開,2025年5月15日参照)より
不登校児童生徒の学ぶ選択肢とその実態
増え続ける不登校への対応として、国や教育委員会等ではどのような施策がとられているのでしょうか? また、実際に不登校になった子どもや家庭にとっては、現状どのような選択肢があるのでしょうか?
文科省の「不登校」に対する取り組み
多様な要因・背景から、結果として不登校状態になっているため、「問題行動」と判断してはならないという認識があり、文科省は2019年の「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知で、
「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく,児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があること。
としています。必ずしも学校への復帰をゴールとはしておらず、学業の遅れや進路選択の際の不利益を被りかねないことなどのリスクも指摘しつつも、多様な関係機関との連携、家庭への支援を基本的な考え方としています。
参考・引用「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(文科省,2019年10月25日公開,2022年10月31日参照)より
COCOLOプラン
2023年3月には「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」が発表され、不登校により学びにアクセスできない子どもたちをゼロにすることを目指して、
- 不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整える
- 心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する
- 学校の風土の「見える化」を通じて、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする
という方針を示しました。具体的には、不登校特例校(学びの多様化学校)や校内教育支援センターの設置促進、1人1台端末を活用した心や体調の変化の早期発見の推進、教師やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどから成るチーム学校による、早期支援の強化等が目指されることとなりました。
2023年6月に閣議決定された教育振興基本計画において、各都道府県・政令指定都市で1校以上を設置し、将来的には全国で300校の設置を目指すことが決定されました。また、同年8月に不登校特例校は「学びの多様化学校」へと改称されました。
参考・引用「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)(文科省,2023年3月31日公開,2025年5月15日参照)より)
参考「第4期教育振興基本計画」(文科省,2023年6月16日閣議決定,2025年5月15日参照)より
教育機会確保法
不登校に関連する法律としては、2016年に教育機会確保法が施行されました。これは、不登校児童生徒を対象とする教育の機会の確保を推進しようという法律で、学校環境の整備、民間団体との連携などを自治体に求めています。
フリースクール等民間団体の支援については直接的に内容としては盛り込まれませんでしたが、不登校児童生徒の状況に応じて「フリースクールなどの民間施設」と連携したうえで「多様な教育機会を確保する必要がある」と明示されています。
参考「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について」(文科省,2016年12月22日公開,2025年5月20日参照)より
参考「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(文科省,2019年10月25日公開,2025年5月20日参照)より
支援機関で学習する児童生徒の出席の扱い
学校外の機関で学ぶ場合、出席の判断はどのようになるのでしょうか。
文科省は学校外の機関での学習が出席に認定されるための要件を「保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。」「当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。」など複数まとめています。
しかし、「適切な支援を実施していると評価できる場合,校長は指導要録上出席扱いとすることができる。」とされ、判断は校長裁量となっています。全国に共通するような明確な基準は示されておらず、運用実態は自治体ごと、学校ごとに大きく差がある状況です。
参考・引用「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)(別記1)義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(文科省,2019年10月25日公開,2025年5月20日参照)より
フリースクール
文科省は、「一般に、不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設」と定義しています。民間の運営による主体性・自主性によって、規模や活動内容は多岐に渡ります。カリキュラムや授業があるところもあればないところもあり、公教育と異なる教育理念や教育方法を採り、学校への復帰にこだわらない団体もあります。比較的少人数で、それぞれが自由に過ごしたり、子ども中心の活動や学習のサポートなどを行っている場合が多いです。
参考「フリースクール・不登校に対する取組」(文科省,2022年10月31日参照)より
教育支援センター
教育支援センター(旧称:適応指導教室)は、学校生活への復帰を目指しその支援をするために設置されている施設です。以前は学校以外の場所に設置されていることが多かったのですが、近年は「校内教育支援センター」として、学校内の空き教室等に設置されることが増えています。個別の学習支援の他、スポーツや芸術、調理体験や自然体験など集団での活動もされています。
参考「「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果」(文科省,2019年5月13日公開,2025年5月20日参照)より
教育支援センターの実態と問題点
教育支援センターは2023年時点で1743カ所設置されており、そのうちの1704カ所が市町村教育委員会による設置となっています。ただし、2023年度で教育支援センターを活用できている割合は、不登校児童生徒の8.8%にとどまり、ニーズに答え切れていない現状です。
また、以前より減ってきてはいますが、「社会的自立」が重要という文科省に対し、「学校復帰」を目標にしてしまっている適応指導教室が多いことが課題とされています。原因は職員に退職教員が多いことなどが挙げられています。
参考「「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果」(文科省,2019年5月13日公開,2025年5月20日参照)より
校内教育支援センター
校内教育支援センターは、教育支援センターの機能を各学校内に持たせたもので、「スペシャルサポートルーム」や「校内フリースクール」などとも呼ばれています。2024年時点で全国の46.1%の公立小・中学校に設置されており、文科省の事業により今後も拡大していく見込みです。
参考「不登校の児童生徒等への支援の充実について(通知)」(文科省,2023年11月17日公開,2025年5月20日参照)より
学びの多様化学校
学びの多様化学校(旧称:不登校特例校)は、学校と同じように出席扱いになる教育機関です。2025年11月現在、全国に58校の学びの多様化学校が設置されています。それぞれに特色のあるカリキュラムや教科を編成しており、不登校経験や、不登校傾向のある児童生徒でも学びを継続しやすい仕組みとなっています。
熱心な取り組みもあり、例えば星槎名古屋中学校は、教師全員がカウンセラーの資格を持っています。共感理解教育を掲げ、生徒もコミュニケーションや心理学を学ぶことができ、生徒同士で助け合える「ピア・チューター」の育成も行っています。
岐阜市立草潤中学校では、個に合わせた多様な学び方を徹底されています。オンライン学習によって家や学校内のさまざまな場所で学習ができ、日々の過ごし方や担任まで個々に応じて見直し、変更することができます。
参考「不登校特例校の設置者一覧」(文科省,2022年更新,2022年10月31日参照)より
参考「学校ブログ 12期ピアチューター研修(養成講座)が行われました!」(星槎名古屋中学校,2022年8月27日公開,2022年10月31日参照)より
参考「注目の不登校特例校「学校らしくない」草潤中の今」(東洋経済オンライン,2021年12月7日公開,2022年10月31日参照)より
支援機関で学習する児童生徒の評価の扱い
これまで、教育支援センターや民間フリースクール、自宅等での学習を適切に評価に反映することが非常に難しい状況が続いてきました。
しかし、2024年8月の「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について」という文科省の通知において、不登校児童生徒に対する支援を強化し、学校以外の支援機関や、自宅でのオンライン学習の学習成果の適切な評価への反映が目指されることとなりました。
学校現場と、フリースクールをはじめとした支援機関が、今後どのように連携や情報共有を深め、子どもたちの学びを保障していくのか、模索が続けられています。
まとめ
不登校という社会課題に対し、社会的な認知も進み、教育機会確保法が制定されたことで学校や民間団体と学校や行政との連携が始まりました。
しかし、不登校傾向も含めると60万人以上と言われる子どもたちの数に対し、公的機関・民間機関を合わせても「学校にかわる居場所・学びの場」は足りておらず、学習権が保障できていないことが大きな課題です。
社会的自立を目標として、多様な選択肢のもとで子どもが学ぶためには、様々な機関の立ち上げや相互の連携が必要です。フリースクールでの学習が出席・単位として認定されたり、教育支援センターの設置が進み学校を中心としない学習の支援が整備されたり、学びの多様化学校の設置の拡大がなされることなどが求められています。また、これらは現在の学校が、不登校状態にある子どもたちを包摂できていないということでもあり、学校がもっとインクルーシブなものになる余地はまだあります。
不登校であっても様々な場所や方法で学ぶことができる「学びの選択肢」が拡大され、そもそも不登校にならなくていいように既存の学校が変容していく、その両輪が回り、噛み合っていくことが求められています。
関連記事
【これからの学校】子どもたちの“SOS”への向き合い方を立場を超えて語り合う
【教職員アンケート】不登校児童生徒の成績評価問題
【保護者×教員対談】不登校をめぐる学校と保護者のコミュニケーション
【インタビュー】不登校だった子どもが変化。担任のアプローチは?
【学校の外部連携】フリースクール運営者から見えること
同じカテゴリの記事
学校教育の知識を増やす

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-
メガホン編集部