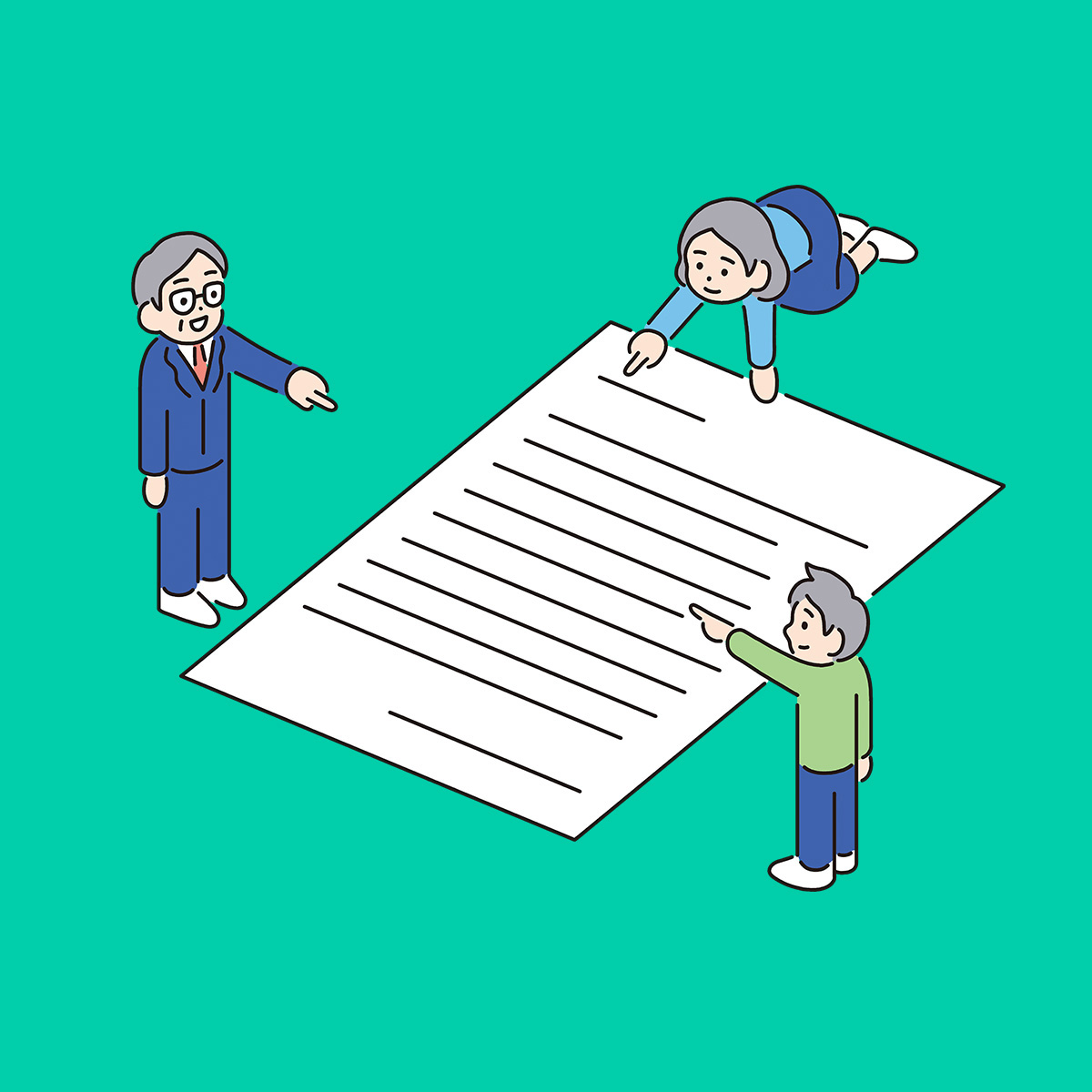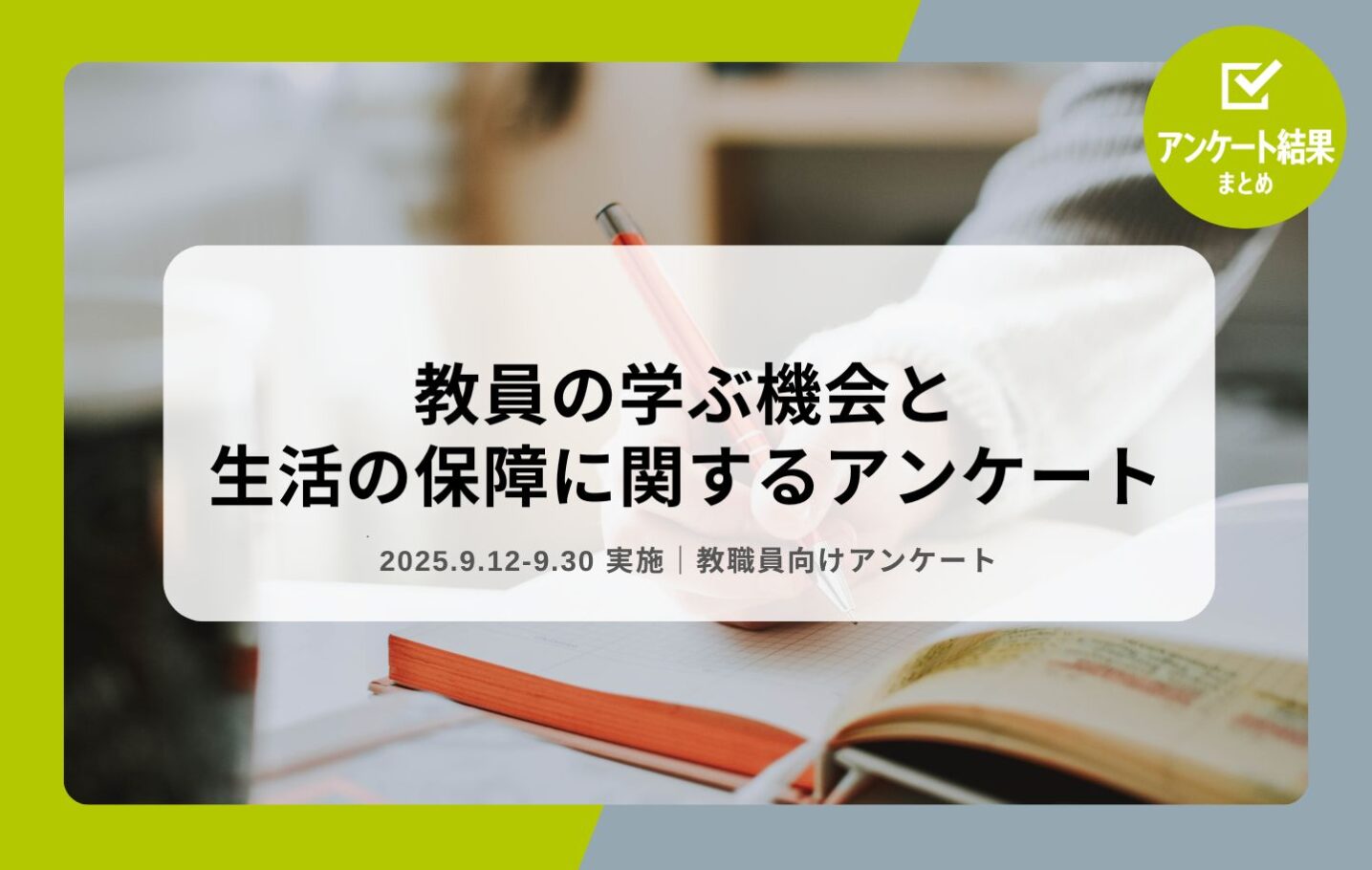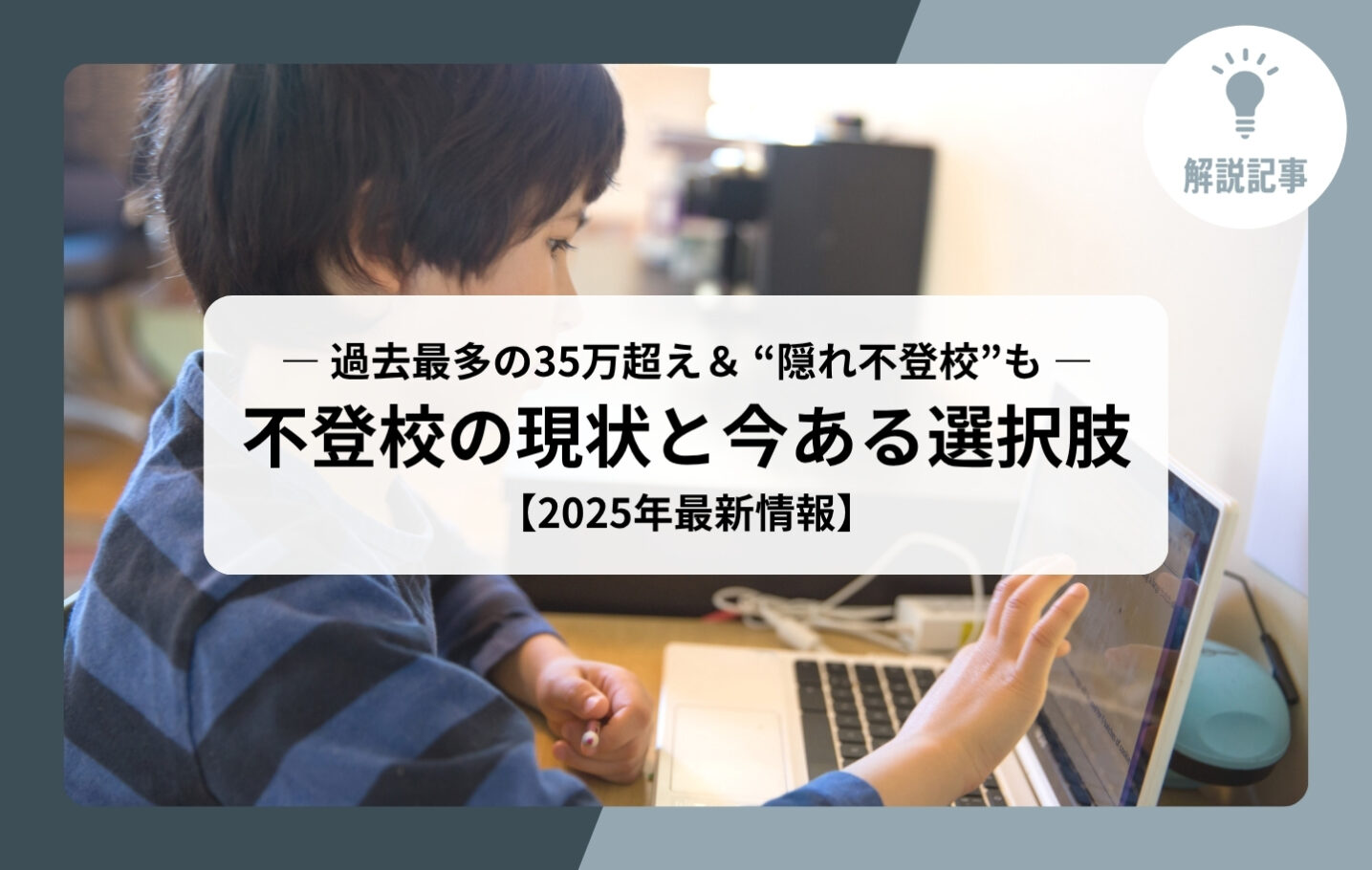不登校35万人時代。子どもたちの“SOS”への向き合い方を立場を超えて語り合う
文部科学省の調査によると、小中学校における不登校児童生徒数は年々増加し、2024年度には35万人に達しました。
なぜ、これほどまでに「学校に行けない」「学校に行かない」子どもたちが増えているのでしょうか。そして、現場の大人たちは何に苦しみ、どうすれば状況を変えられるのでしょうか。
今回は、教員、支援者、保護者という立場の異なる3名が集まり、それぞれの視点から見えてくる「不登校のリアル」と、これからの学校のあり方について語りました。
参加者

藤倉 稔(ふじくら みのる)さん: 北海道の小学校・中学校で計18年間の教員経験を持つ。現在は小学校勤務。不登校問題に高い関心を持ちつつも、現場での対応の難しさに葛藤する。自身の子どもも不登校を経験。NPO法人School Voice Project理事。

齋藤 暁生(さいとう あきお)さん: 元中高教員。現在は独立し、オンラインフリースクールの立ち上げや、不登校の子ども向けのサービス「ユルタ」などを展開。NPO法人School Voice Project理事。WEBメディア「メガホン」ではシステム管理を担当しており、不登校解説記事の編集にも携わった。

梁井 利恵子(やない りえこ)さん: 3人の子どもを育て上げた保護者であり、そのうち1人が不登校を経験。現在は「親カフェ」を主催し保護者が安心安全におしゃべりできる場づくりをする傍ら、在住市のこどもの居場所ネットワーク事業の地域コーディネーターをしている。
不登校が増える背景にあるもの
不登校の児童生徒数が過去最多を更新し続ける中、皆さんはそれぞれの現場で、今の子どもたちの状況をどう見ていますか?
藤倉: 正直なところ、うちの子が学校に行けなくなったときもそうでしたが、「理由がよく分からない」というのが実感です。本人も分かっていないし、親も分からない。何か発達的な要因があるかもしれないし、家庭に不安要素があって元気がなくなっているかもしれない。本人の中でも整理できていないストレスが蓄積しているように感じます。
でも、学校側はそこまで深く踏み込めず、わかってあげられないもどかしさがあります。軽々しく「学校においで」とは言ってはいけない状況があるにもかかわらず、立場上そう言ってしまう……。そこに難しさを感じています。
梁井: 子どもって、良い意味でも悪い意味でも、社会を映し出す鏡のような存在ですよね。日本の社会全体が不穏だったり、歪みが出ていたりすると、子どもたちはそれを敏感に感じ取って、自分の体や心を使って警告を鳴らしているんじゃないかと思います。
齋藤:すごく分かります。社会の歪みのしわ寄せが、一番弱い立場である子どもたちに来てしまっている。僕は、数字の面からも今の状況を危惧しています。メガホンの不登校記事でも取り上げたんですが、公表されている不登校児童生徒の数以外に、実は“隠れ不登校”がたくさんいると思っています。
文科省は年間30日以上欠席した子どもを理由別に集計しているんですが、このうち“病気”を理由にした長期欠席の子が、ここ数年で数万人単位で増えているんです。病気の子がそんなに急増するはずがないので、実態は不登校に近い子が含まれているはずです。
さらに、学校には行っているけれど「ちょっと行きたくないな」と感じるときがある子や、年間30日以上は欠席してないけれど休みがちな子を含めると、裾野はかなり広い。僕の肌感覚では、100万人くらいの子が何かしらの「学校への行きづらさ」を抱えているのではないかと思っています。
※ 文部科学省の調査では、児童生徒が「病気」「経済的理由」以外の要因によって年間30日以上登校できなかった場合を不登校として集計しています。
学校に来ている子もしんどさを抱えている
藤倉: 学校に来ている子たちだって、本当に学校を楽しんでいるかというと疑問です。「学校に来ているから大丈夫」とも言えないんですよね。
以前担任していたクラスで、子どもたちに学校評価のアンケートをとったことがありました。「学校は楽しいですか?」という質問に対して、勉強もできて活発で外遊びも大好きな子が、「うーん、中休みと昼休みがあるから、楽しいことにしておこうかな」と言っていたんです。
僕ら教員から見れば「学校生活を満喫している」と思える子でさえ、楽しみは休み時間だけ。その出来事があって、楽しみを感じずに学校生活を送っている子は多いのではないかと気付かされました。
梁井: 昔、息子が学校に行けなくなったとき、たまに登校する日があったんです。すると先生に、「来ると元気なんですよね」って言われたことがありました。その言葉はつらかったですね。
めちゃくちゃ元気に見えるんですよ、表面上は。でも、それは無理しているだけで、心から楽しんでいるわけじゃない。それなのに「元気なんだから、来ればいいじゃん」と思われてしまうんです。
齋藤: 先生たちが「学校は大事だよ」「勉強は大事だよ」と言い過ぎていることも、子どもたちを追い詰める一因かもしれません。もちろん、先生としての立場は分かるんですが、社会全体が「もっと頑張れ」「学校に行くのが正しい」というメッセージを出しすぎて、子どもたちが無理をしてしまっているように思います。
梁井: 本当は「学校が大事」なんじゃなくて、「その子が幸せに生きていくこと」が大事なはずですよね。学校はそのための手段の一つでしかないのに、いつの間にか逆転してしまっている。
藤倉: 僕自身の話をすると、子どもの頃はよく「死にたい」とか「いなくなりたい」と考えていました。でも、当時はSNSもなかったから、比較対象が周りの友達くらいしかいなかった。
今は違いますよね。スマホを開けば、世界中のキラキラした幸せそうな人たちが目に入ってくる。僕の子ども時代でさえつらかったのに、今の情報量で同じように悩んでいたら、本当に追い詰められてしまってもおかしくないなと思います。
齋藤: ネット上のやり取りも影響していますよね。SNSで「学校に行きたくない」と呟くと、見ず知らずの大人から「学校は行ったほうがいい」とコメントがついたりする。
不登校の子だけでなく、その予備軍の子たちがそれを見て、「今はつらいけど、やっぱり無理してでも行かなきゃいけないのかな」と自分を追い込んでパンクしてしまうケースも見てきました。大人の何気ない正論が、ネットを通じて子どもたちの首を絞めている側面もあるのかもしれません。
大人たちも抱えている苦しさとは
今、子どもたちが苦しんでいる一方で、学校現場の先生たちもまた、かつてないほど疲弊しているように見えます。
藤倉: そうですね。まず、教員が圧倒的に足りていません。不登校対応にかけられるリソースがほとんどないのが現状です。
本当は、子どもとゆっくり話して関係をつくりたいんです。中学校では空き時間に「公園に行って話そうか」なんてこともできましたが、小学校では担任がずっと教室にいなければならないので、物理的に無理なんです。子どものつらさを聞いてあげたいのに、その時間も余裕もなくて、結局「学校に来ないから、何もできない」で終わってしまう。そのもどかしさは常にあります。
齋藤: 先生方の余裕のなさが、職員室の空気を殺伐とさせている側面もありますよね。
藤倉: それはすごく感じます。不登校が増えているという現状に対し「学校に来ないのは、すぐに休ませる家庭の問題だ」など、親や子どものせいにしてしまう教員の声がSNSでも上がっていますよね。不登校の裏には「“昭和”の学校と“令和”の子どもたちのミスマッチ」というような構造的な問題があると思うんですが、そこに目を向けるゆとりすらない。
体罰ができなくなった分、言葉による暴力や、冷たい対応が増えているようにも感じます。僕自身も、忙殺される中で、のんびりしている子に対してきつい言い方をしてしまったりして反省することがあります。
齋藤: 評価や提出物のプレッシャーも大きいですよね。先生たちも本当は子どもに無理をさせたくないのに、管理職やシステム上の要請で「宿題はやらせろ」「テストは受けさせろ」と言わなきゃいけない。
藤倉: 今、デジタル化が進んでいて、タブレット上で「誰がテストを受けていないか」が一目瞭然なんですよ。教育委員会や管理職からチェックが入るから、久しぶりに登校した子に、たまったテストを5枚まとめてやらせて帰らせる、なんてことも起きてしまう。せっかく来たのに、ただ消耗させて帰らせてしまうんです。
梁井: 先生たちも本当に大変なんですよね。だから「学校が悪い」「先生が悪い」と責めても解決しない。
ただ、子どもが不登校になってしまうと、親としては、地域の情報やセーフティネットから一気に孤立してしまう恐怖があるんです 。だからこそ、お互いに苦しい中でどうつながり続けるか、大人が一度立ち止まって話し合う必要があると感じます。
学校はどう変わっていくべきか
先生も親も、そして子どもも苦しい。この袋小路を抜けるためには、どんな変化が必要なのでしょうか。
藤倉: 自分自身の反省でもあるんですが、これまで僕は真面目すぎたなと思っていて。「学校に来るなら朝から来るべきだ」と、どこかで求めてしまっていました。
でも、もっと柔軟でいいはずなんです。「給食だけ食べに来る」「休み時間だけ遊びに来る」とか。僕らが勝手につくった“登校のハードル”を下げて、「そういう登校もOKだよね」と認めてあげる。最近では「マイスタイル登校」という言葉もありますが、まさにそうやって個々のスタイルを尊重できれば、もっと救われる子は増える気がします。
梁井: まさにそうだと思います。イベントの名前なんかを考えるときにも思うんですが、「不登校」と言うと、どうしても否定のニュアンスが入ってしまうし、言葉として強すぎる。でも、検索されるのはその言葉だったりするから難しいんです(苦笑)。
齋藤: 本当は「学校に行くか、行かないか」という「0か100か」の二択ではないはずなんですよね。「最近、ちょっと疲れているから週2回にする」とか、「今日は元気だから朝から行く」とか、もっとグラデーションがあっていいと思っています。
「学校はもっと柔軟でいい」ということに関しては、「休んだ子の学びのフォローが大変で教員の負担が増えるのでは?」といった意見もあると思います。その点についてどう思いますか?
齋藤: 教員時代に私が自由進度形式で授業を行っていたときは、授業の受け方を生徒が選べる形だったため、教員側の負担を高めることなく授業に柔軟性を持たせられていたと思っています。中には、部活の大会で公欠になる生徒もいれば、体調や気分の波で「昨日は集中できなかった」という生徒もいました。けれど、どんな理由であれ、それぞれが自分のペースで遅れを取り戻したり、先へ進めたりしていました。
もちろん、それ以外でもさまざまな工夫の余地があると思っているので、先生たちや学校の工夫で「柔軟さ」と「負担減」の両立を目指していけるといいですよね。
梁井: 大人の社会では「フレックスタイム制」や「テレワーク」が広がってきていますよね。大人の働き方はどんどん多様化して、在宅勤務も選べるようになっているのに、学校だけが「8時から夕方まで全員集合」というスタイルが変わっていないように思います。
齋藤: そうなんです。社会で必要な能力も変わってきていて、「毎日決まった時間に決まった場所に行く能力」だけが全てではなくなっています。
だからこそ、完全にパンクして長期の不登校やひきこもりになる前に、「カジュアルに休む」という選択肢が必要なんです。僕が今進めている「ユルタ」というサービスもそうなんですが、「今日は学校を休んでこっちに行こう」と気軽に選べる場所をつくりたいと思っています。
現在は不登校の子どもの学習支援を通じて自己肯定感を高めたり、子どもが学校を“安心して休める”環境をつくっているんですが、将来的にはもっと幅広い子どもに向けたサービスにして、“学校に行きたくない日にふらっと使えて心が休まる居場所”をつくりたいと思っています。

最後に、これからの学校のあり方に対する思いや願いを聞かせてください。
藤倉: 僕は、もっと子どもたち一人ひとりの状態に合わせたアプローチができたらと思っています。今は「不登校」とひとくくりにして対応していますが、先生に会うのもつらい子もいれば、学校行事だけは参加したい子もいる。それなのに、同じ対応をしてしまっている気がするんです。
そして何より、その細かな対応をするための「暇がない」という現実があります。子どものことを見てあげたいのに、見る余裕がない。話したいのに、教科の指導やテストに追われて話す余裕もない。それでは、子どもが不登校になっても状況を理解できず、対応が遅れてしまったり、保護者とのやり取りが遠くなったりしてしまう。こういう学校現場の構造が変わっていくことを願っています。
梁井: 難しいことだと思いますが、私も、やはり学校というシステム全体の変革が必要だと感じています。先生たちがもう少し増えるとか、余裕ができるようになるとか。いろんなカリキュラムも含めて、全体が大きく変わるといい。
同時に、学校とそれ以外との間の垣根が低くなるといいなと思います。学校外の人間からすると、学校の先生や関係者の方とコミュニケーションを取るハードルが高すぎるなと感じるので、もう少し柔軟な方法はないのかなと。そして、いろんな立場の大人たちが、今の子どもたちがしんどいことや、自分たち自身もしんどいことを、いい意味で“ざわざわ“対話できるといいなと思っています。
齋藤: 大前提として、学校も家庭も、すべては子どもが幸せに生きるための手段でしかない、というところは絶対に忘れてはいけないと思っています。この根本に立ち返り、大人たちが「学校に行くことが絶対じゃないんだ」という意識を持った上で、苦しみすぎずに、気楽に支え合える社会になるといい。
不登校が35万人を超える状況は、もはやクラスの中の「特殊な子」の問題ではなく、社会全体のシステムをアップデートする時期に来ているということです。この認識を、広く持っていくことが重要だと思います。
同じカテゴリの記事
学校教育の知識を増やす
教職員の声に触れる
学校に関わる人の声から学ぶ

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-
メガホン編集部