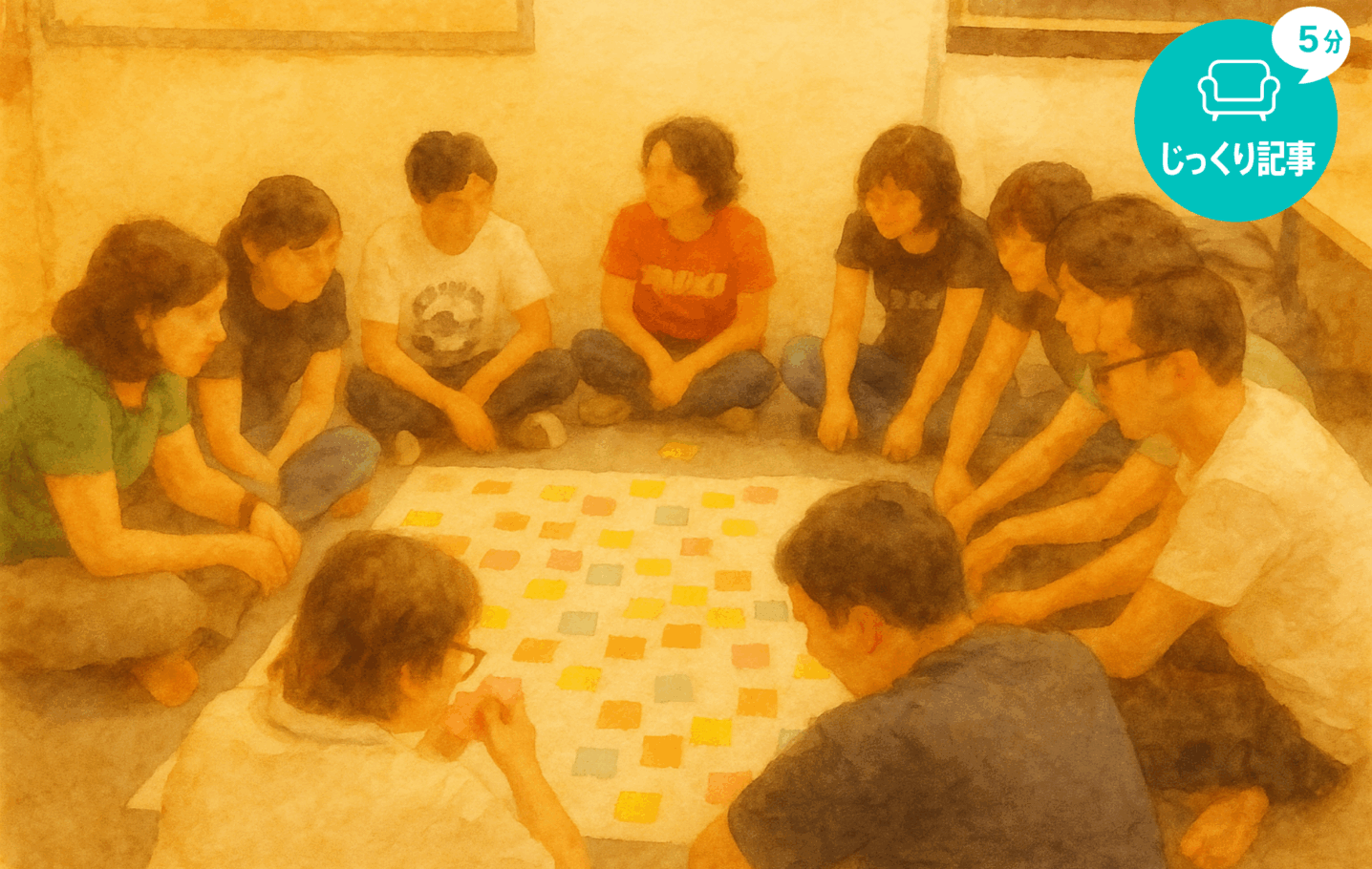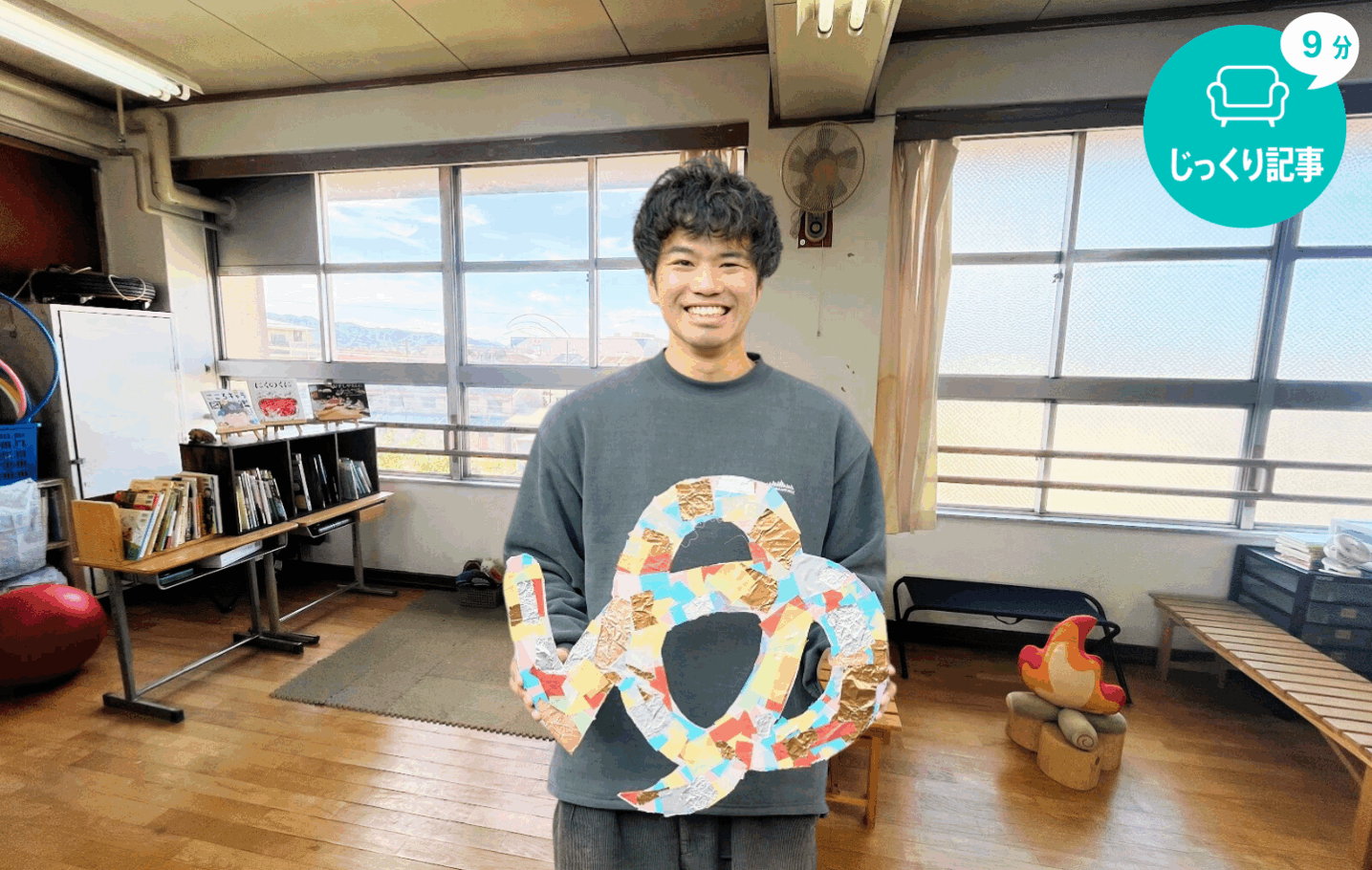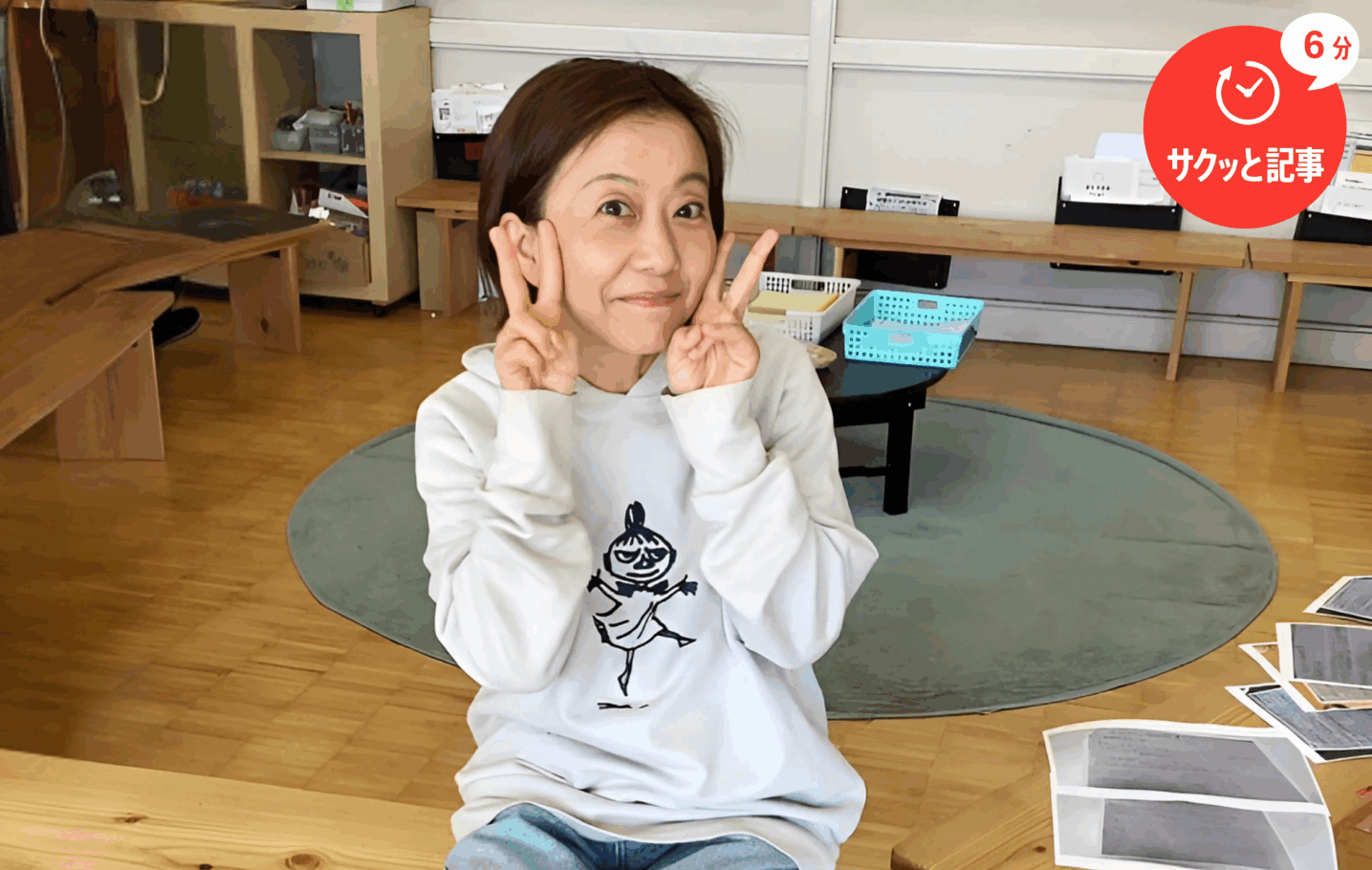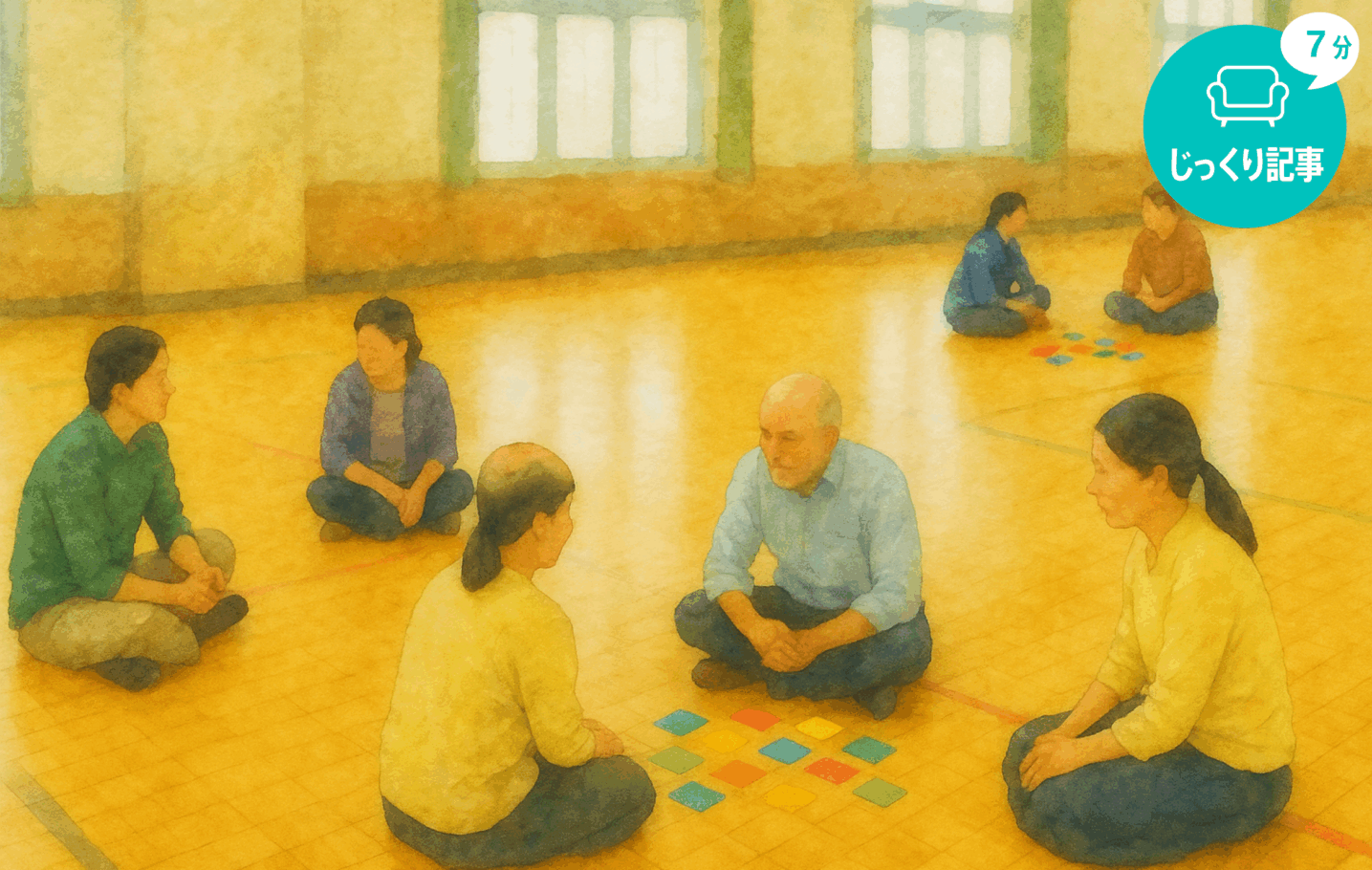
【前編】“痛み”の感情を分かち合うことで、先生をつなぐ。沖縄の小学校で生まれた校内研修
学校現場で働く先生たちは、日々子どもたちと向き合う一方で、自分自身のことを語る機会はなかなかありません。
「自分の弱さを嘆く場があれば、つながりが生まれ、チームは前に進み出す」
そう信じて実践を重ねてきたのが、沖縄県うるま市の公立小学校で校内研(副)担当を務める親田拓之さんです。
校内研(副)担当として2年目を迎える今、親田さんが校内研主任の先生とともに進めているのは「嘆きの共有の場」と「プロジェクト型研究」。どちらも、先生たちが安心して本音を出し合い、主体的に学び合えるようにと工夫された取り組みです。
それらはどのように生まれ、学校にどんな変化をもたらしているのでしょうか。その背景と取り組みについて、お話を伺いました。前編と後編に分けて、お届けします。
休日の職員室が、“憩いの時間”だった
——— どのようなきっかけで、校内研修を担当することになったのでしょう?
前任校での経験が大きかったですね。小規模校で、人の距離も近くて。子どもの声を聞いて、それを翌年度の学校運営に反映させるような仕組みをつくることもできました。子どもと先生と地域が、一緒に学校をつくっている。そんな実感が強くて、本当に楽しかったんです。
なので、異動で今の勤務校に赴任したときは、「学校を変えてやる!」と意気込んでいたのですが……正直、空回りでしたね。子どもの声はなかなか拾えないし、自分のやりたいこともうまくできない。しかもコロナ明けで、子どもたち同士も隣りの子とあまり話さないような状態でした。
それで、気づいたんです。「まずは先生たちとつながらなきゃ」と。もちろん子どもとの関係も大切ですが、この学校では先生たちとつながることから始めないと前に進めないと感じました。
——— なぜ、先生との関係性に意識が向いたのでしょう?
私は土日もよく学校に行っていたのですが、決まって顔を出す先生が何人かいたんです。あるとき、その中の1人が「しんどいんですよね」とこぼしたら、別の先生が「私もなのよ」と返したんです。その先生は、私から見れば「すごくできる先生」だったので、その言葉には驚きました。さらに別の先生からも、しんどさや上手くいかなさを耳にするようになりました。
そうやって弱さを共有できるのが、私にとっては“憩いの時間”でした。土日に少し話すだけで「しんどいよね」とお互いに言い合える。それで、生き延びていたんです。
この経験を通じて、職員同士が悩みを共有し合える「嘆きの対話」の大切さに気づきました。そして、「もっと深く対話について学びたい」「対話を通して支え合える関係を築きたい」と強く思うようになりました。それで、「対話の場をつくりたい」と校長に直談判したんです。校長は賛同してくれて、校内研修を担当させてもらうことになりました。
——— 校内研修の新たな実践が始まったのですね。
そうです。ただ、一部の先生からは「対話なんて、必要あるの?」という反応もありました。そんな状態から始まったんです。

「おしゃべりがしたい」から始まった、対話の場
——— 対話の場をつくることに対して、不安を感じる声もあったのですね。そのような状況の中で、何から始めたのでしょう?
まずは先生たちに「次年度、校内研修で何をやりたいですか?」と聞いてみたんです。具体的な意見がなかなか出ない中で、あるベテランの先生がポツリと「私はもう、おしゃべりがしたいわ」と言ったんです。その瞬間、「来た!」と思いましたね。「おしゃべり、いいですね! じゃあ、おしゃべりしましょう」と即答しました。そして「来年度の校内研修は、おしゃべりです」と宣言してしまったんです(笑)。
ただ、先生方がイメージしていた「おしゃべり」は、職員室の奥の給湯室でお菓子をつまみながら雑談する感じ。もちろんそういう時間もいいのですが、私はそれを「対話」として、もう少し意味あるかたちにできないかなと思ったんです。
そこで、SEL(Social and Emotional Learning:ソーシャル・エモーショナル・ラーニング)をベースとしたプログラムを全国の学校や大学に導入する支援をしている「株式会社 rokuyou(ロクユウ)」さんに連絡をしました。知人がメンバーの1人だったこともあり、以前からrokuyouさんのされていることに興味があったんです。
「次年度、校内で対話の場を本格的につくりたいので伴走をお願いできませんか?」とお願いすると、ありがたいことに快諾してくださり、翌年度(2024年度)4月からrokuyouさんに伴走してもらうことが決まりました。あのときに一緒に動いてくださったことには、本当に感謝しています。
先生方には、「4月からrokuyouさんに伴走に入ってもらいます!」と、半ば強引に伝えました。もちろん「外部の人が入るの?」「ろくゆうって何?」という不安の声もありましたが、ともかくスタートラインには立つことができたんです。
——— 先生の声を拾いながら、いろんな方の協力を得て進めていったのですね。ただ、民間企業に依頼するには予算が必要ですよね。そこはどうやったのでしょうか?
本当にラッキーだったんです。ちょうどその頃、rokuyouさんも「学校現場に入って、SELの実践の場をつくりたい」と考えていたんです。さらに、財団からの支援もあり、活動資金を持っておられました。
もちろん、学校として無料で伴走をお願いするわけにはいかないので、一部はうるま市の予算で支払うことになりました。資金面の後押しがあったおかげで、rokuyouさんに入ってもらうことができたんです。
“先生”を外して、人として語り合う
——— それで2024年4月から、新しい校内研修がスタートしたわけですね。具体的に、どんなことをしたのでしょうか?
まずは、先生同士の関係づくりとして、4月に「人生の道」というワークを行いました。これまでの人生でのアップダウン――「このときは調子が良かったけれど、ここで落ち込んだ」などをワークシートに書き出し、4人1組で語り合うんです。ここでは、教員としての経験だけでなく、自分自身の人生の歩みや心の浮き沈みを抵抗のない範囲で語ります。
先生たちは普段、子どもや学級のことを語る機会は多いのですが、自分自身の人生を語る場はほとんどありません。だからこそ、先生という肩書きを外した“人”として、まずはつながってほしかったんです。
さらに、先生たちが疲れを感じやすい6月と10月には、「エンパシーサークル(共感サークル)」を実施しました。これは非暴力コミュニケーション(NVC:Nonviolent Communication)の実践方法のひとつで、輪になって座り合い、互いの気持ちや大切にしていることに耳を傾け合うように対話をしていくんです。
rokuyouさんが開発された「感情対話カード」を使いながら、自分の今の気持ちを表す「疲れている」「悲しい」「楽しい」などのカードを選び、それをもとに話していきます。聴き手はアドバイスをせず、ただ聴き切ることに集中します。その後、周りの先生たちが「この感情の背景には、こんなニーズがあるのでは?」と、カードを通して話し手に伝えていきます。

——— この時間には、どのようなねらいがあるのでしょう?
人と人がつながるとき、もちろん「楽しい」「嬉しい」といった感情の共有は大切です。でも、実は「悲しい」「不安」といった痛みの感情を分かち合うことでも、深いつながりが生まれると思っています。
むしろ、そこにこそ人を結びつける力があると感じるんです。先生たちも子どもたちも、本当はどこかに痛みを抱えていることがある。その部分を安心してさらけ出せたとき、初めて「信頼関係」が生まれ、「同じチームとして前に進める」という実感が湧いてくるんです。
なので、対話の場ではあえてその「痛み」に焦点を当てています。シンプルですが、自分の感情に気づき、それを言葉にし、周りに受け取ってもらう。その経験が「ここでは嘆いてもいいんだ」という安心感を育ててくれるんです。この時間を、「嘆きの共有の場」と呼んでいます。
——— 聴き手のあり方も、場の空気に影響しそうですね。話し手が話しやすい雰囲気をつくるために、工夫されていることはありますか?
エンパシーサークルを始める前に毎回やっているのが、「聴き方」の確認です。最初に「ジャッジせずに聴きましょう」「アドバイスはぐっとこらえて、ただ耳を傾けることに徹しましょう」と必ず伝えています。つい「こうしたらいいよ」と言いたくなるのが人間ですが、それを抑えて、今回はただ聴く。そこをみんなで合意してから始めるようにしています。
実際にやってみると、相手に共感できる喜びや、自分が共感される喜びを体感できる。そういう経験が積み重なると、「人の話をただ聴く」ことの意味が実感として分かってくるんです。「嘆きの共有の場」は、その大切さを一緒に学べる時間にもなっていますね。
後編へ続きます。
同じカテゴリの記事
実践を知る|職場づくり・組織開発

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-
建石尚子