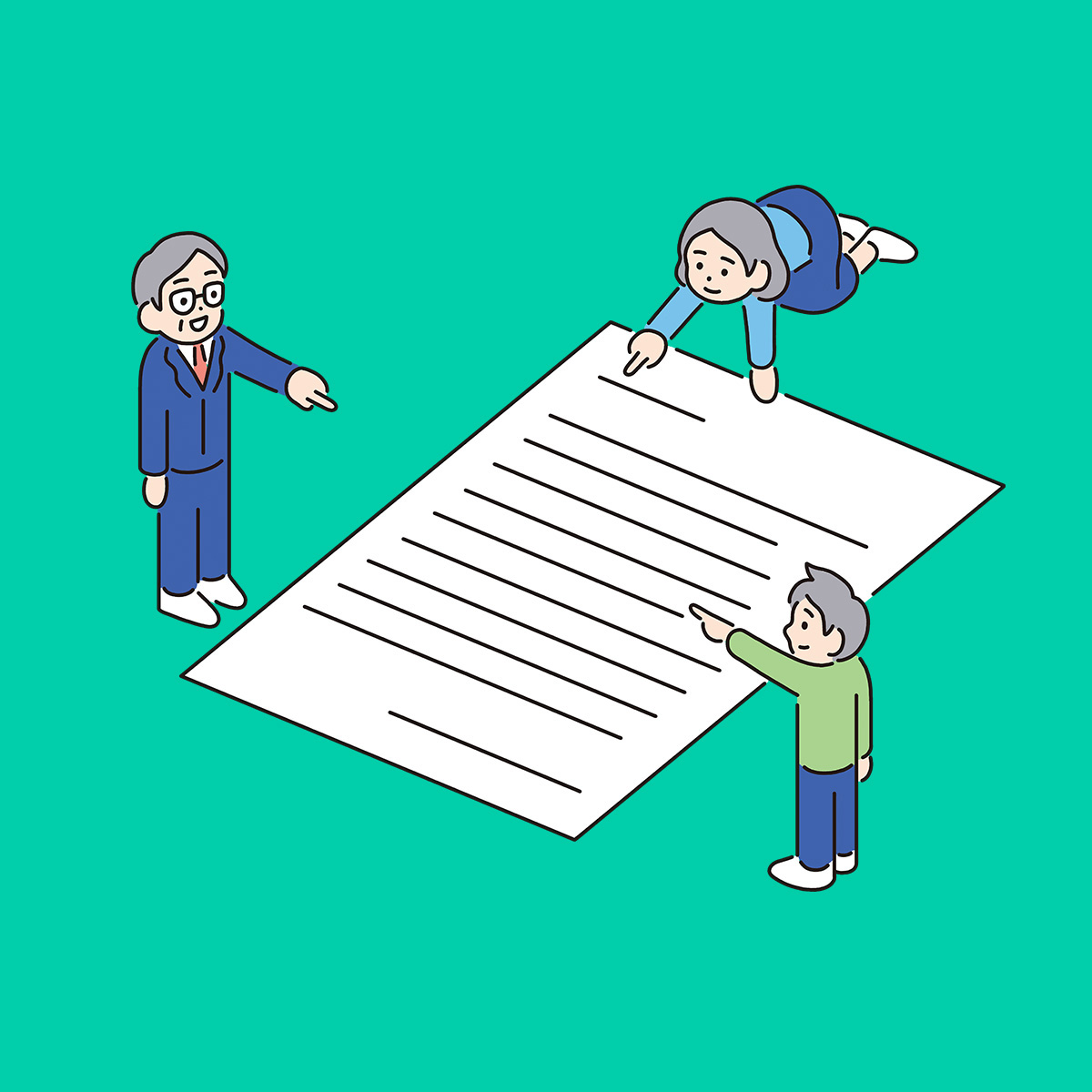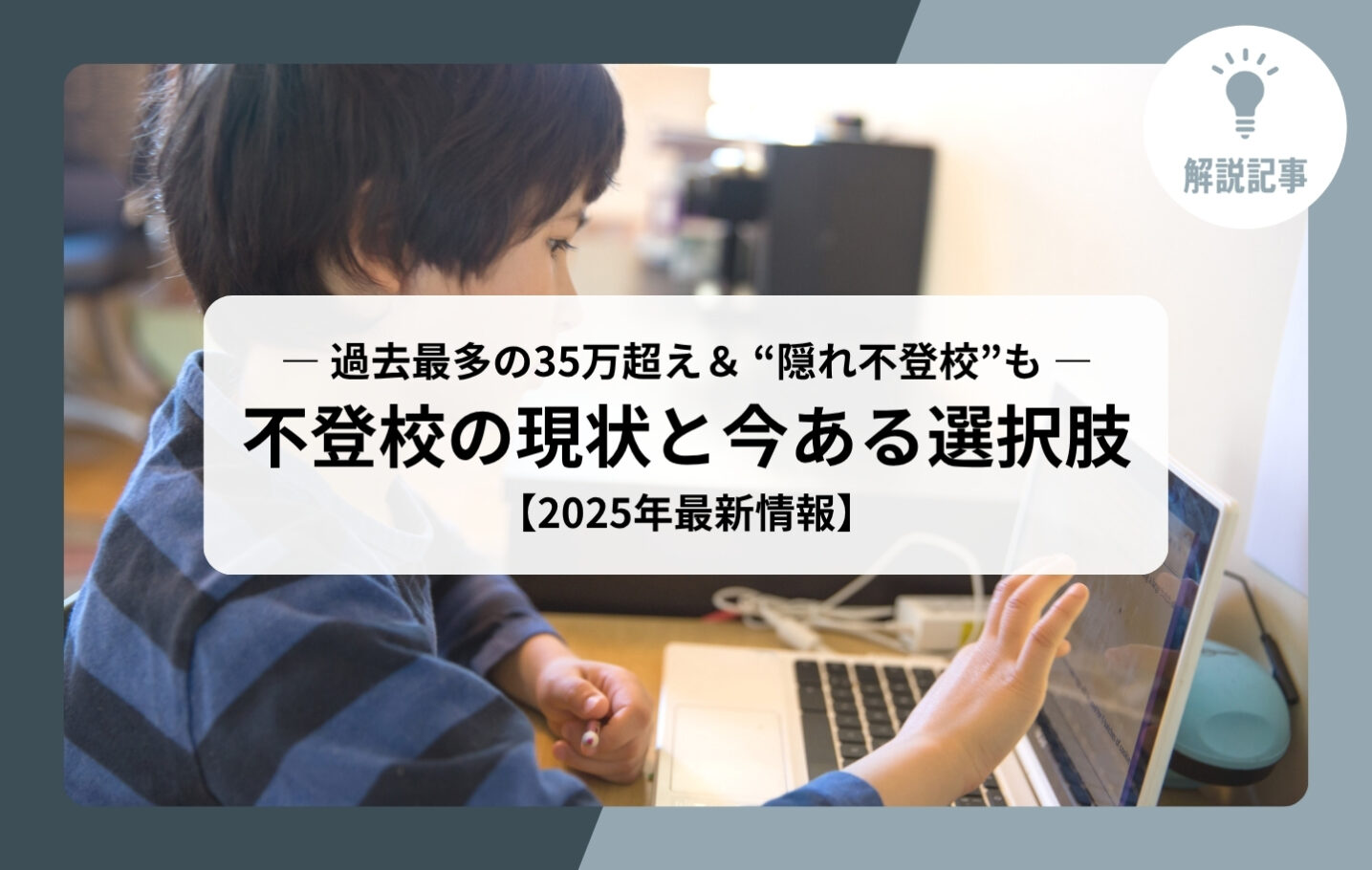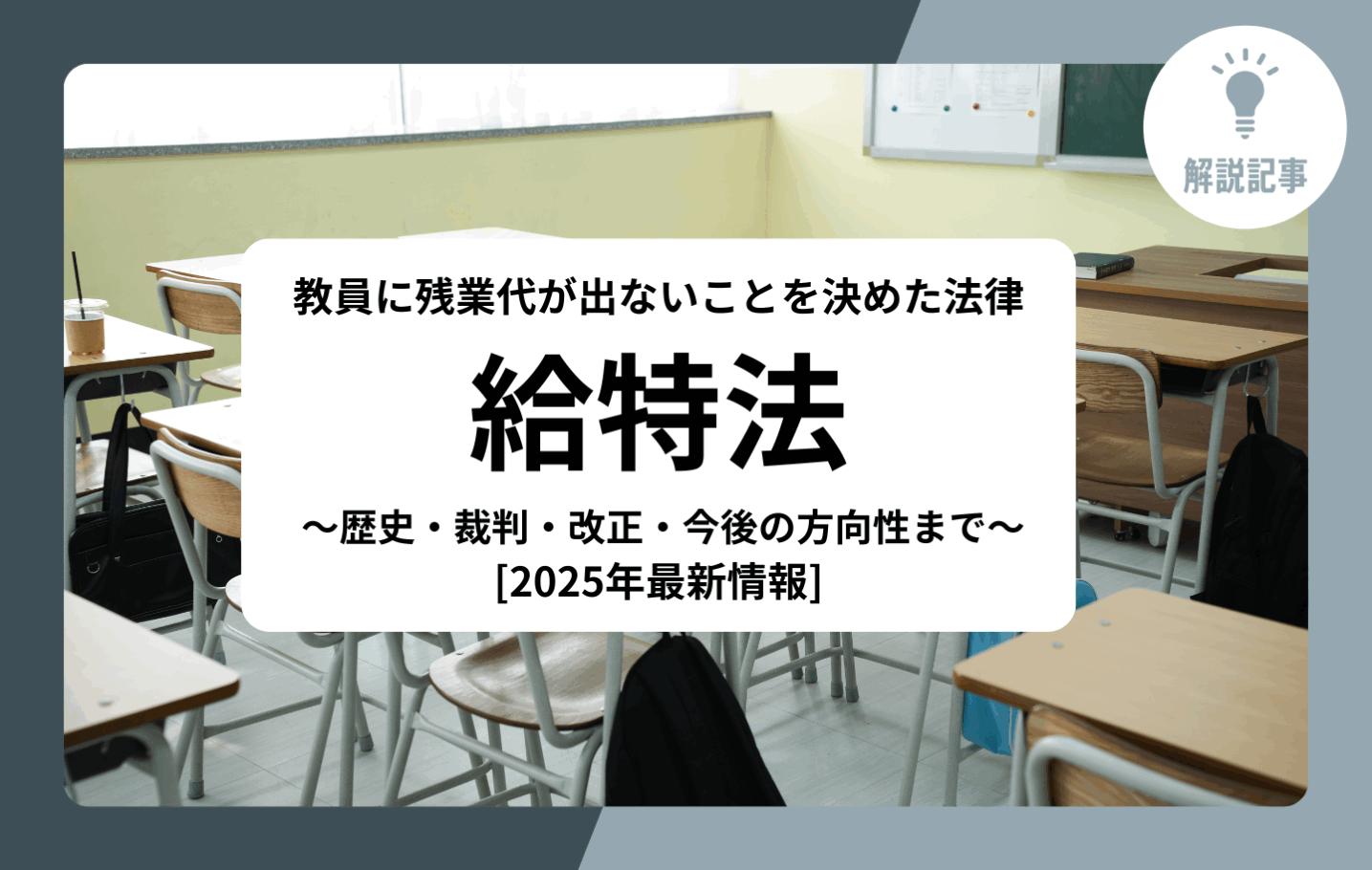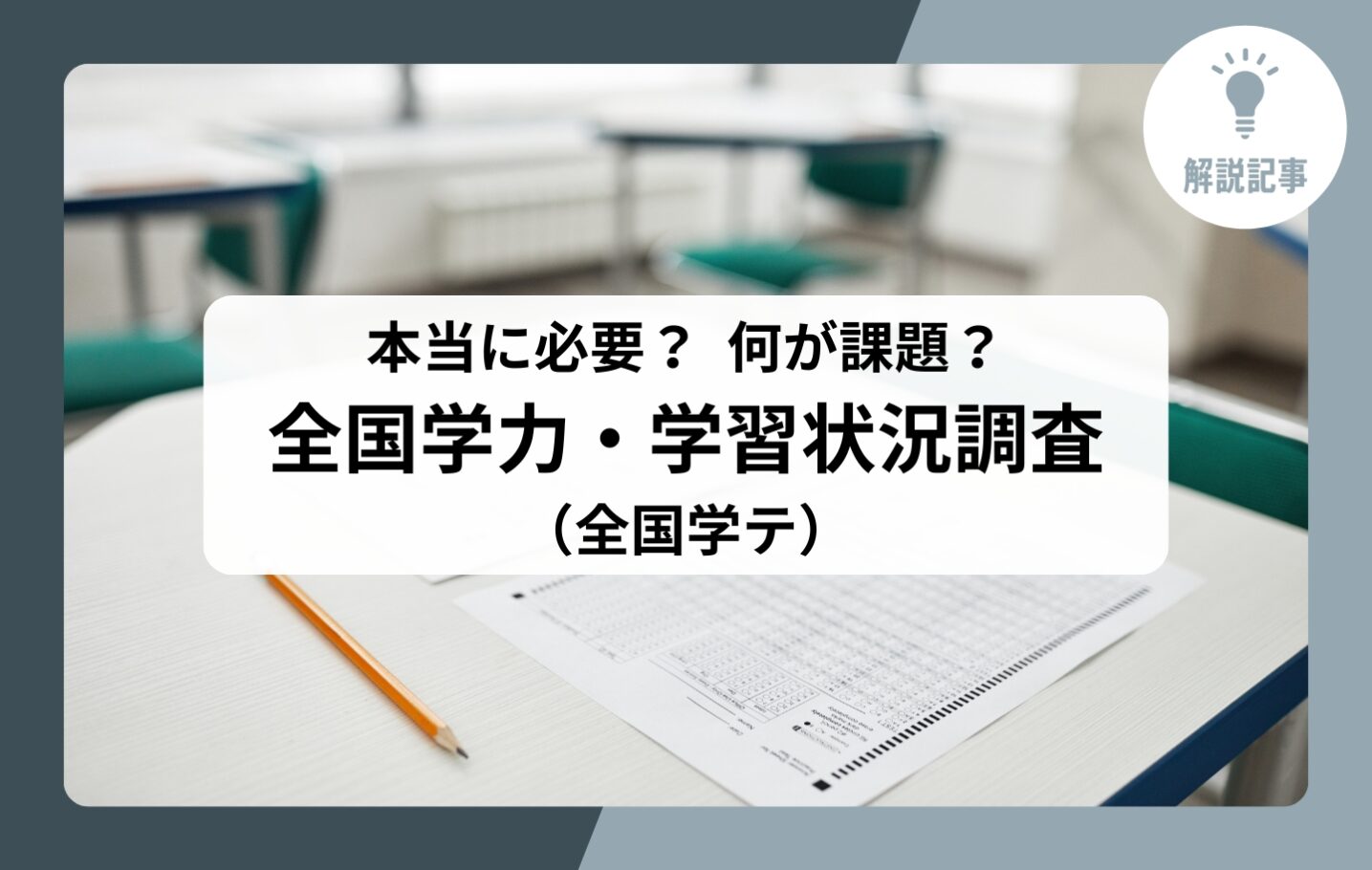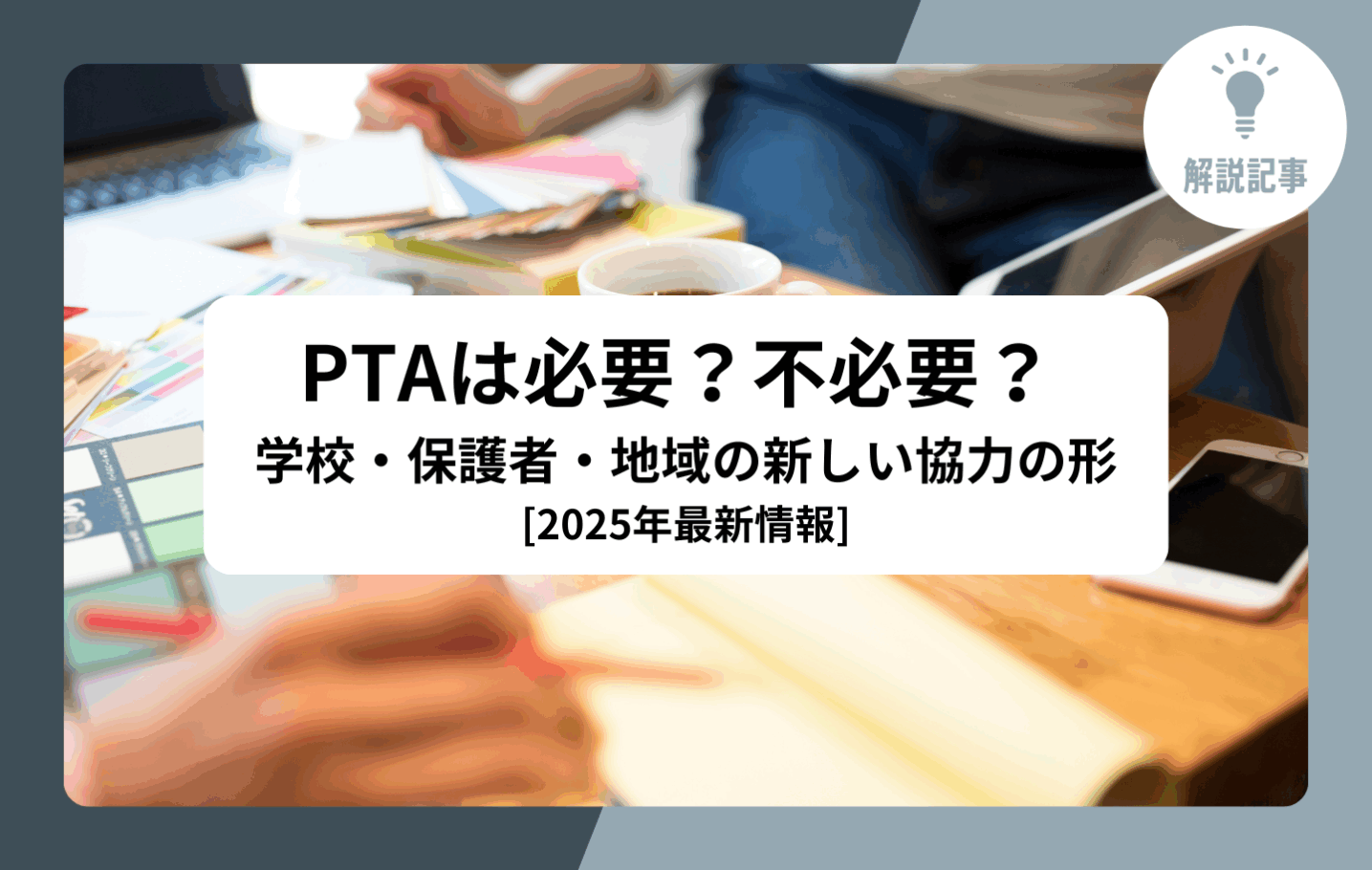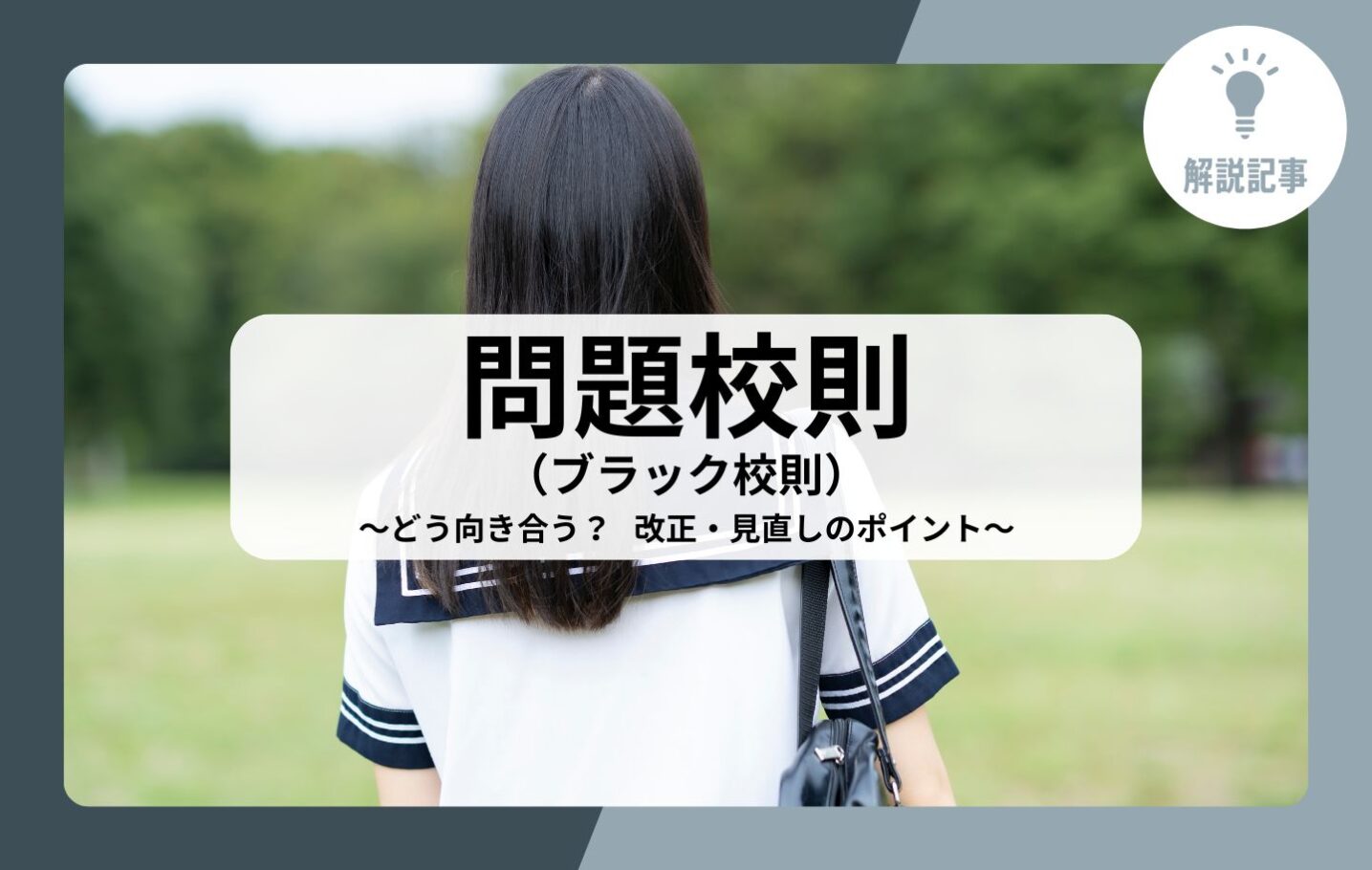
【解説記事】[2025年最新情報]問題校則(ブラック校則)、どう向き合う? 廃止・見直しのポイント
「校則見直し」どうすればいい? その意義と方法
前ページでは、問題校則のどこが問題であるか、またどのように見直しの気運が広がっているかについて解説しました。それでは、自校で校則見直しに取り組む際には、具体的にどのように取り組みを始めればよいのでしょうか。ここでは、校則見直しの意義と方法、そして実際に校則の見直しと改定が行われた2つの例を紹介します。
校則見直しの意義
校則見直しにあたっては、見直したい校則の性質によってその問題点と見直す意義が異なるため、アプローチの方法も変わることに留意する必要があります。
① 人権問題に直結するような校則(=「問題校則」)
② そのほかの(靴下の色指定などのような)人権侵害とまでは言えないような校則
①に関しては、残しておくこと自体が人権侵害に繋がるため、その校則に関わる大人が早急に変える“義務”があるとも言えます。
一方で②に関しては、生徒指導提要にもある通り、児童生徒が規則を改正するプロセスを経験し、自分たちのものとして守っていこうとする態度や主体性を養う機会とすることに意義があります。
②について、熊本大学教育学部准教授である苫野一徳氏も、校則見直しによって自分たちで学校をつくり合う経験が得られることに着目し、「市民社会の担い手を育てる」ことにつながると述べています。
苫野一徳准教授:
市民社会において学校は自分たちの学校を自分たち自身でつくり合う経験を保証する必要があります。そもそも子どもたちが学校をつくりあげるという経験を積まずにどのようにして市民社会の担い手を育てるのかという話になります。若者が政治に興味がないと言われることが多いですが、自分たちの社会を自分たちでつくるという経験を積んでいないので、興味をもちにくいのも当然のことです。そういう意味で、学校とは市民を育む場であるという本質に照らして自分たちでつくり合う必要があります。
引用「【校則の捉え方を対話を使って見直す】決定版 令和の校則 苫野一徳先生講演録」(EDUPEDIA,2022年1月24日公開,2025年9月1日参照)より
「社会」の視点から「校則見直し」にどう向き合うか
ここまで「校則見直し」について、ポジティブな意見や取り組みを紹介してきました。ここであらためて、学校を取り巻く「社会」の視点から「校則」を見てみましょう。
「問題校則」は当然、見直されてしかるべきですが、「風紀を気にする地域住民」や「学生はこうあるべき」という社会からの有言無言の要請が「校則」というルールを作り上げた側面もあるのではないでしょうか。見直しに消極的な方の中には「学校の評判が悪くなる」「地域や社会がそれを求めているから必要だ」と考える人もいるでしょう。
しかし、例えば校則に何の規定もなく「自由な服装・髪でOK」となり、ユニークな恰好、髪の学生に対して眉をひそめる人がいた際に、「服装や髪の毛でその人を判断するのは偏見です」と言えるでしょうか。これは、教員や学校を取りまく社会が、どのように人を判断し、何を求めるのかという、社会全体の問題であるとも言えます。
みんなのルールメイキングプロジェクトの取り組み
探究学習支援のマイプロジェクトなどに取り組むNPO法人カタリバは、2019年に「みんなのルールメイキングプロジェクト」を開始しました。このプロジェクトは校則や学校内のルールの見直しを「学校ルールメイキング」と位置づけ、生徒主体の対話を通じて実施する仕組みを広げていくもので、2019~2022年度には経済産業省「未来の教室」実証事業にも採択されました。単にルールを変更することが目的ではなく、「生徒・教員・保護者などが対話を重ね、納得感のある合意形成を行う」という過程を重視している点が特徴で、2025年時点で全国の500校以上が参加しています。
活動内容
① 実証事業校へのコーディネーター派遣による伴走支援
② 自治体主導によるルールメイキング活動の推進支援
③ ルールメイキングに取り組む個人・学校・自治体への教材提供や実践導入サポート
④ 校則・ルール見直しに関する指針「みんなのルールメイキング宣言」の作成・普及
また、2025年には教員向けガイドブック『児童・生徒とともに作る学校 POINT BOOK』を公開し、課題の見える化から合意形成、検証までの5つのステップを示すとともに、校則以外にも学校行事や授業運営など幅広いテーマに応用できる仕組みを整えています。
取り組みと効果
実際にルールメイキングを行う学校に対しては、校則改訂に向けたプロジェクト設計や、生徒・教員・保護者との対話の場づくりを支援しています。さらに、導入を検討する個人・学校・自治体に向けても、教材・研修の提供や、他校の教員や生徒との交流イベントの実施などを通じて導入を後押ししています。
これらの取り組みの効果について、2025年に実施された調査(生徒・教員232名対象)では、生徒の約6割が「意見を聞く場がある」と実感しており、生徒の声を聴く機会が多い学校ほど見直しが進んでいる傾向が見られました。また、教員の9割以上が「生徒の意見を取り入れるべき」と回答しており、ルールの変更だけでなく「意見を聞き、応答し、反映する循環」を設計することの重要性が示されています。
参考「みんなのルールメイキングプロジェクト | 活動紹介」(認定NPO法人カタリバ,2025年9月1日参照)より
参考「“子どもの声を学校づくりに活かす実践”をまとめた教員向け実践ガイド 『児童・生徒とともに作る学校POINT BOOK』を公開」(認定NPO法人カタリバ,2025年6月19日公開,2025年9月1日参照)より
参考「校則見直し、進む学校と進まない学校の間に「生徒の意見を聞く機会がある」という実感」(認定NPO法人カタリバ,2025年6月19日公開,2025年9月1日参照)より
校則の変革事例
保護者や地域から意見を募り、生徒が主導して校則を変える
「みんなのルールメイキングプロジェクト」に参加している岩手県立大槌高校では、かつて「ツーブロック禁止」の校則がありましたが、生徒が「なぜ禁止なのか」と疑問を持ち、地域企業・役場・保護者にアンケート調査を実施しました。その結果、多くの声から「ツーブロックでも気にしない」との理解が得られ、髪型に関する校則は「高校生として清潔感や節度のあるもの」に改定されています。
また、このプロセスを通じて教員側もそれまでの「既存の校則を教員側が守らせ、生徒は校則を守るべきだ」という一方通行の指導から、「生徒と一緒に校則を見直し、生徒自身がつくった校則を自分たちで守った方が良い」という考えに変わったと言います。担当教員の熊谷さんは、教員自身にとっても、校則を見直すことによって納得感のある指導ができるようになったと振り返ります。
参考「「なによりも、生徒と“一緒に”校則をつくっていくというプロセスに価値がある」先生たちに聞きました〜みんなのルールメイキング活動レポートvol.4〜」(認定NPO法人カタリバ,2021年5月24日公開,2025年9月1日参照)より
教員と生徒が協働して校則を見直す
愛知県の逢妻中学校では、赴任したばかりの教員が中心となり、生徒とともに校則の見直しに取り組みました。有志の生徒が加わって「校則検討委員会」を立ち上げ、全校アンケートや意見交換を行いながら検討を進めました。その結果、半年ほどの活動を経て複数の校則が改定されました。
この過程を通じて、教員が主導するのではなく、生徒が主体となって全校に活動を広げていったことが特徴であり、校則が「守らされるもの」から「自分たちでつくり、守るもの」へと意識が変化するきっかけとなりました。
参考「【事例】赴任したばかりの学校で「校則の見直し」を全校活動にできた理由とは。現職教員が語る。」(認定NPO法人カタリバ,2024年11月21日公開,2025年9月1日参照)より
市をあげて「幸せな学校づくり」を推進する
茨城県つくば市では、2022年から市立手代木中学校と島名小学校をモデル校として、校則や学校生活のルールを生徒・児童とともに考える取り組みを始めました。子どもたちは「幸せな学校づくり」をテーマに意見を出し合い、その声は学校や市教育局、大学関係者とも共有されました。
この取り組みは校則の見直しにとどまらず、学校生活全体の在り方を児童・生徒が主体的に考える契機となり、地域や行政と連携した新しい学校文化の形成につながっています。
参考「つくば市の小中学生が「幸せな学校づくり」事例を発表、官民連携で児童・生徒主体の学校をつくるルールメイキング最前線セミナー開催」(認定NPO法人カタリバ,2024年2月9日公開,2025年9月1日参照)より
メガホンでは、認定NPO法人カタリバと共同開催したイベントについて、レポート記事も公開しています。ぜひあわせてお読みください。
まとめ
問題校則とはどのようなものであるか、またそれに関する世の中の動きや、校則見直しの意義、取り組み例について説明しました。
2022年12月の「生徒指導提要」改訂を機に、日本の校則をめぐる状況は決定的な転換点を迎えました。理不尽な校則の存在を告発する段階から、いかにして民主的で教育的なプロセスを通じて見直していくかという「実践」の段階へ移行しています。
この移行を支えるのは、①国の基本方針として生徒参加や情報公開を定めた「生徒指導提要」、②校則の運用や指導の妥当性を厳しく問う司法の潮流、そして③NPOなどが専門的な方法論で学校現場を支援する体制の構築という3つの柱です。
子どもが自分たちの学習環境を自ら整え、主体的に社会に参画していくためにも、校則見直しを重要な教育活動と捉え、学校や社会が対話・議論を重ねていくことが、今後も重要なプロセスとなりそうです。
さらに、国会でも校則の制定・改廃プロセスに生徒や保護者の意見を反映させることを義務付ける学校教育法改正案が提出されるなど、議論は国政の場にも及んでいます。校則問題は、単なる教育実践の問題から、学校のあり方そのものを問う法制度の問題へと変化していると言えるでしょう。
参考「【法案提出】「学校内民主主義法案」を参議院に提出」(国民民主党,2025年3月19日公開,2025年9月1日参照)より
関連記事
同じカテゴリの記事
学校教育の知識を増やす

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?
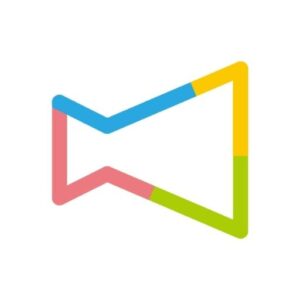
-
メガホン編集部