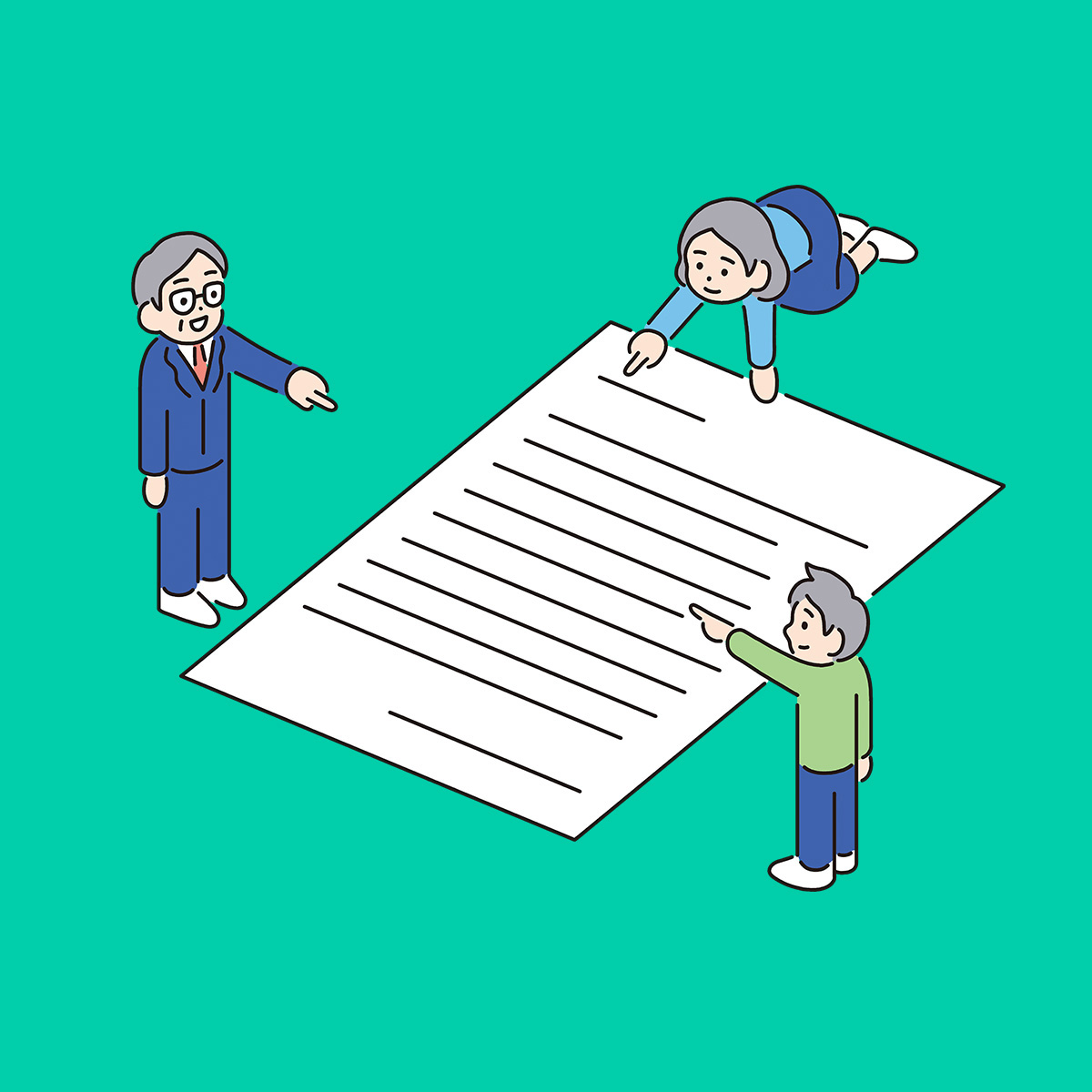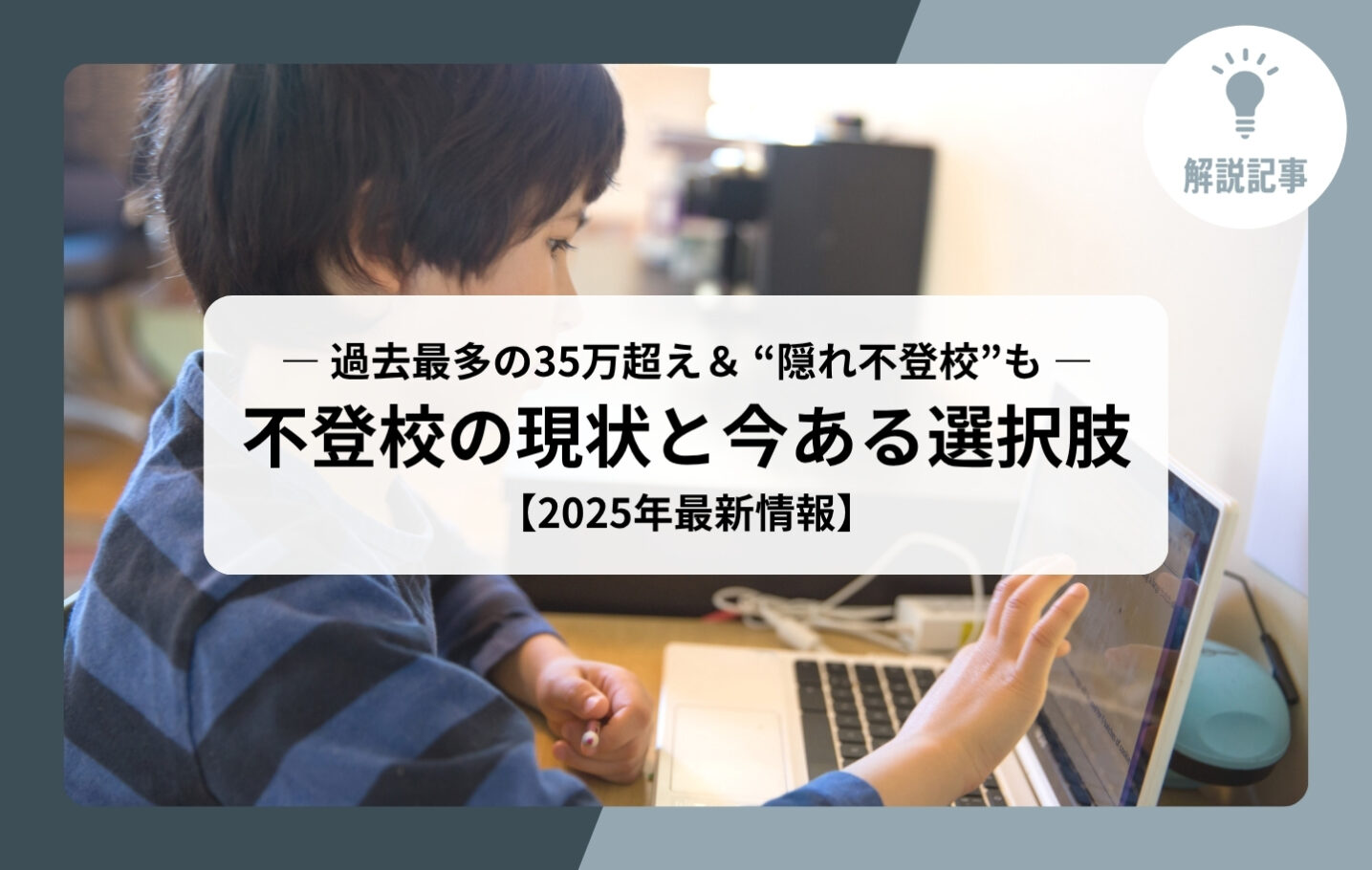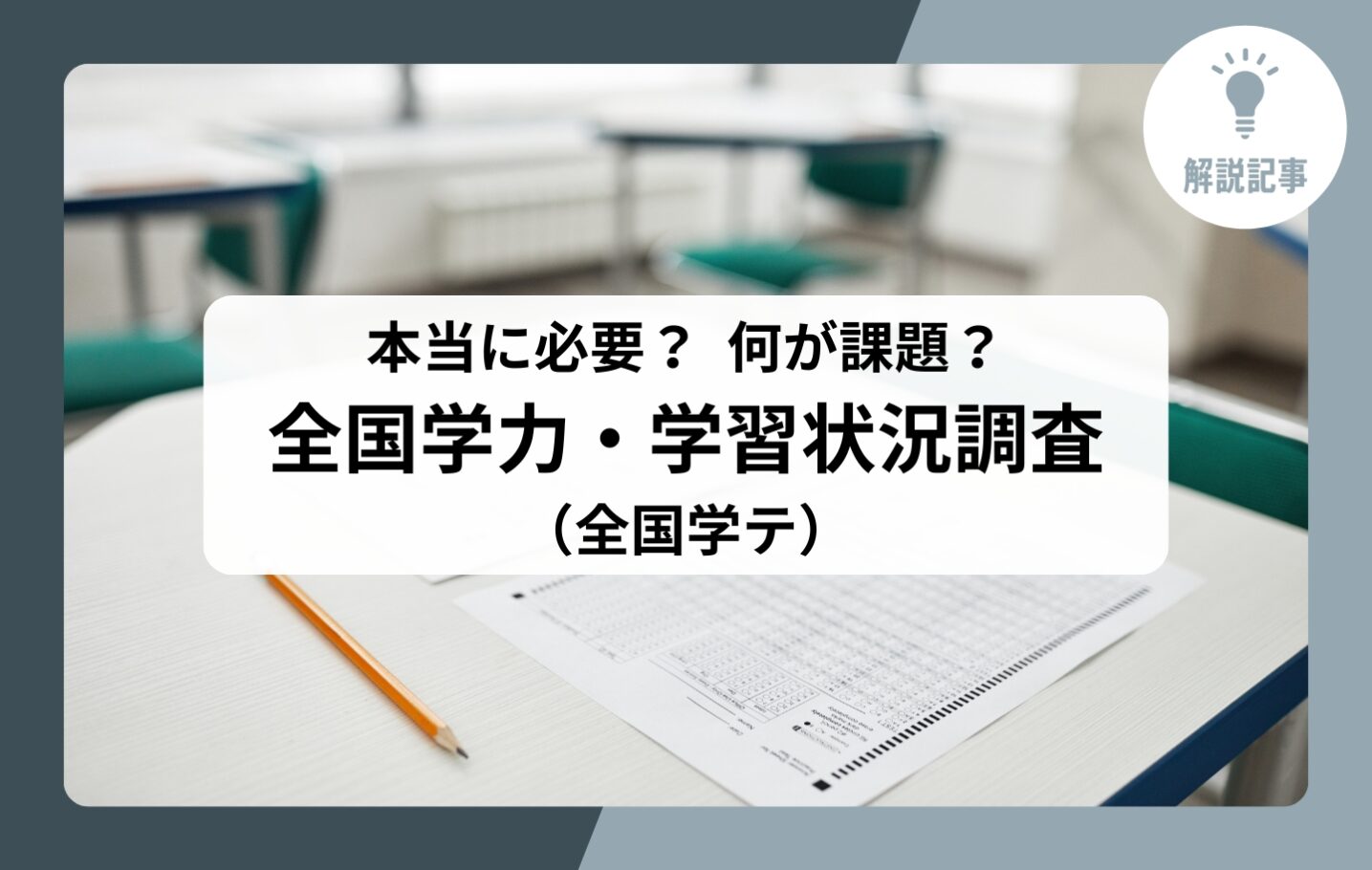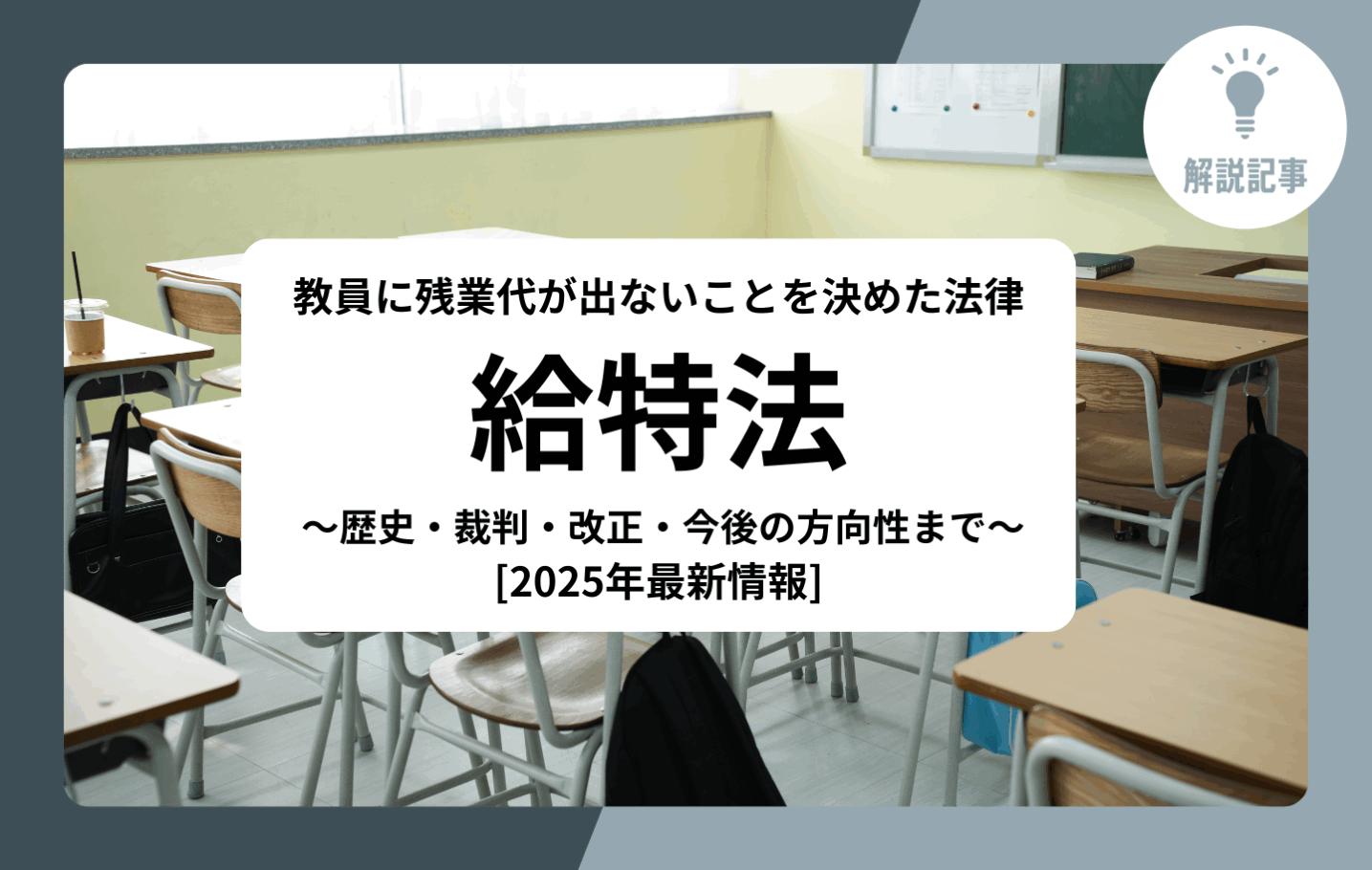
【解説記事】[2025年最新情報]教員に残業代が出ないことを決めた法律、給特法 ~歴史・裁判・改正・今後の方向性まで~
残業代が出ない長時間勤務をはじめとした、公立学校の教員に課せられた過酷な労働条件が、日本の教育が直面する喫緊の課題として、今まさに大きな転換点を迎えています。2024年8月の中央教育審議会(中教審)の答申を受け、教員の処遇を抜本的に改善するため、給与に一律で上乗せされる「教職調整額」を現行の4%から10%に段階的に引き上げることを柱とする改正給特法が、2025年6月11日に可決・成立しました。
この法改正は、教員の長時間労働が授業の質の低下や心身の健康問題、さらには深刻な教員不足を引き起こしているという危機感の表れです。しかし、この処遇改善に対しても、現場の教員や専門家から「問題の根本解決にはならない」との批判も根強く、議論は続いています。
この記事では、そもそもなぜ教員に残業代が出ないのか、その根拠となる「給特法」の歴史的背景と構造を振り返ります。その上で、最新のデータで見る教員の過酷な勤務実態、司法が警鐘を鳴らした様々な判決結果、そして成立した改正法を巡る様々な論点を深く掘り下げ、日本の教育の未来を左右するこの問題の全体像を分かりやすく解説します。
なぜ教員には残業代が出ないのか?
教員に残業代が出ないことを決めた法律、給特法
なぜ公立学校教員に残業代が支給されないのでしょうか。その法的根拠は、1971年に制定された法律、いわゆる「給特法(*1)」にあります。
給特法は、教員に対し、給料月額の4%を「教職調整額」として支給する(3条1項)代わりに、時間外勤務手当と休日勤務手当を支給しない(3条2項)と規定しています。
そして、あくまで例外的に教員に時間外勤務をさせる場合があると6条で示し、その具体例を政令(*2)で定めています。
では、具体例とはどのようなものでしょうか。政令は、時間外勤務に「臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限る」と条件を付け、
- 校外実習その他生徒の実習に関する業務
- 修学旅行その他学校の行事に関する業務
- 職員会議に関する業務
- 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
という、4種類の業務(いわゆる超勤4項目)に絞って時間外勤務を命じることを認めています。
*1 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」
*2 「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」
引用「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(e-gov,2025年7月14日参照)より
引用「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」e-gov,2025年7月14日参照)より
給特法ができた経緯
① 戦後すぐから議論が始まる
一般公務員には、残業時間に応じて時間外勤務手当が支給されるのに、なぜ給特法は、公立学校の教員には残業代を支給しないと明記しているのでしょうか。その背景には、教員の勤務時間を厳密に管理するのが難しいという特殊性があります。つまり、教員は子供の「人格の完成」を目指す教育を職務とするため、日々変化する子供に向き合う上で自主性、創造性が求められ、どこまでが業務でどこからが自主的な行為なのが線引きが難しいためです。
教員の特殊な勤務環境に対し、どのような給与体系で報いるべきかという問題は、戦後間もない頃から長きに渡って議論の対象となってきました。
文部科学省がまとめた資料(*)によると、例えば早くも1948年の給与制度改革で、教員は特殊な勤務体系で長時間労働が多いとして、給与を一般公務員より1割ほど高くすること、そして超過勤務手当を支給しない代わりに、原則として超過勤務を命じないことが決められています。
* 「昭和46年給特法制定の背景及び制定までの経緯について」(文科省,2025年7月14日参照)
引用「給特法に規定する仕組みの考え方 ~給特法の制定経緯から~」(文科省,2018年10月15日,2025年7月14日参照)より
② 社会問題化し、給特法の成立へ
公立学校の教員に残業代を支給しないと定めた給特法は、一見教員に対して不利なようにもみえます。しかし、歴史的経緯を見ると、給特法は本来、教員の待遇を改善するために制定された法律だと分かります。給特法の現在の姿を検討する前に、制定当時(1971年)に国が想定した本来の趣旨を確認してみましょう。
戦後、勤務環境の特殊性から、教員の給与が一般公務員より引き上げられた一方で、1960年代に入ると教育現場で教員の超過勤務がより目立つようになりました。また、一般の公務員の給与体系は年々改定され、教員との給与差は少なくなっていきました。このため、1960年代には教員が超過勤務手当の支払いを求める行政訴訟が全国で多発し、「超勤問題」として社会の注目を浴びました。文部省(当時)は、人材確保のため教員の待遇を改善する必要にも迫られ、超過勤務の実態調査に乗り出しました。この調査結果を踏まえ、国会で様々な議論を経て、1971年に給特法が制定されました。
引用「教職調整額の経緯等について」(文科省,2025年7月14日参照)より
③ 給特法制定当時の状況
それでは、給特法が制定された当時、教員はどのような環境下で働き、給特法の制定によって、どのくらい待遇が改善したのでしょうか。
給特法は、文部省(当時)が1966年度に全国の教員の勤務状況を1年かけて調査した結果を踏まえ、1971年に制定されました。調査結果によると、当時、全国の教員の超過勤務時間は平均で月間8時間ほどだったため、給特法は毎月8時間の残業代に相当する金額として、給与月額の4%を「教職調整額」として支給することを定めました。
同時に、給特法は「教職調整額」の支給を定める代わりに教員には時間外勤務手当を支給しないこと、そしてそもそも、教員に原則として時間外勤務を命じないこと、命じる場合は、①生徒の実習に関する業務、②学校行事に関する業務、③教職員会議に関する業務、④非常災害等のやむを得ない場合(いわゆる超勤4項目)に限ると定めています。
そして、重要なことですが、給特法に定められた「教職調整額」は、制定当時の割合(4%)から50年以上もの間、一度も変更されていませんでした。2025年に行われた法改正は、半世紀という長い時を経た一歩だったと言えるでしょう。
現在の教員の「働き方」と合ってる?
最新データから見る勤務実態
かつて教員の待遇を改善し、人材を確保するために1971年に制定された給特法。制定に向けて国が実態調査を行った1966年度当時、全国の教員の超過勤務時間は平均で月間8時間ほどでした。それでは制定から50年以上が過ぎた今、教員の勤務実態はどうなっているのでしょうか。改めて、今なお給特法が十分に教員の待遇を保障できているかみてみましょう。
文部科学省が2022年度に行った最新の「教員勤務実態調査」によると、「教諭」の1日当たりの平均在校時間は、平日で小学校が10時間45分、中学校が11時間1分に達します。土日で小学校が36分、中学校が2時間18分でした。正規の勤務時間が7時間45分であることを考えると、毎日3時間以上の残業が常態化していることが分かります。前回2016年度の調査からはわずかに減少したものの、依然として極めて長い時間です。
また、同調査の週当たり総在校時間から月の時間外勤務を計算すると、国のガイドラインである「月45時間」を超える教員は小学校で64.5%、中学校で77.1%に上ります。さらに、「過労死ライン」とされる「月80時間」を超える教員も小学校で14.2%、中学校で36.6%存在するなど、給特法制定時の「月8時間」から時間外勤務が大幅に増えていることが分かります。
参考「教員勤務実態調査(令和4年度)集計【確定値】 ~勤務時間の時系列変化~」(文科省,2025年7月14日参照)より
参考「1日あたりの勤務時間数は減少するも、平均在校時間は依然として10時間以上」(独立行政法人 労働政策研究・研修機構,2023年8月,2025年7月14日参照)
海外との比較
諸外国と比べても、日本の小中学校の教員の労働時間は際立って長いのが実情です。
OECD加盟国等48か国・地域が参加した調査「TALIS 2018」によると、2018年の日本の教員の1週間当たりの仕事時間は、小学校54.4時間、中学校56.0時間。参加国平均(中学校)の38.3時間を大幅に上回り、参加国の中で最長でした。
しかし、この調査で注目すべきは、その時間の「使い方」です。日本の教員の授業時間(中学校で18.0時間)は、実は参加国平均(20.3時間)よりも短いのです。では、なぜ総労働時間が最長になるのでしょうか。
その理由は、授業以外の業務負担の重さにあります。特に、部活動などの「課外活動の指導」に費やす時間は、日本の中学校教員は週平均7.5時間と、参加国平均(1.9時間)の約4倍に達します。また、報告書作成などの「一般的な事務業務」も、参加国平均の2倍以上の時間を費やしています。
その一方で、職能開発に充てる時間は日本は参加国平均(2.0時間)の半分以下(小学校0.7時間、中学校0.6時間)に過ぎず、「海外と比べ授業時間は少ないものの、課外活動や事務作業に時間がとられ、必要なスキルを身に付ける時間も確保できない」という教育現場の現状が浮き彫りになっています。
引用「我が国の教員の現状と課題 – TALIS 2018結果より–」(文科省,2025年7月15日参照)より
参考「OECD国際教員指導環境調査(TALIS)」(国立教育政策研究所,2025年7月15日参照)より
「残業代が出ないこと」のもたらす歪み
司法からの警鐘
1971年に制定された給特法は、原則として教員に時間外勤務を命じてはいけないと定めているのに、なぜ現在、日本の教員の労働時間が過大になっているのでしょうか。その背景には、時間外の業務の多くが「教員の自発的行為」とみなされ、使用者である教育委員会の責任が問われにくいという構造的な問題があります。しかし近年、この「常識」に司法が切り込む動きが相次いでいます。
大きな転機となったのが、埼玉県の公立小学校の教員が残業代を求めた訴訟です。2021年10月のさいたま地裁判決では、原告の請求自体は棄却されたものの、判決文の最後に裁判官が異例の「付言」を加えました。その中で、「 給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」と明確に指摘し、「勤務実態に即した適正給与の支給のために、給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め 、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望む」と、立法府に法改正を促したのです。
画期的な「宿泊学習」判決
さらに画期的だったのが、2025年3月に高松地裁で下された判決です。香川県の元中学校教員が、宿泊学習の引率中に十分な休憩時間が与えられなかったとして県を訴えた裁判で、裁判所は労働基準法違反を認定し、県に5万円の損害賠償を命じました。この判決は、教員の時間外労働をめぐる議論において、極めて重要な意味を持っています。
判決の核心は、「給特法があるから残業代は出ない」という大きな壁に対し、「休憩時間の付与」という労働基準法上の基本的なルールは給特法でも排除されない、という新たな法的解釈を示した点にあります。裁判所は、宿泊学習が学校長の具体的な計画の下で業務内容やスケジュールが厳格に管理されており、教員の自由な裁量の余地はないことから、これは給特法が想定する「自発的行為」ではなく、明確な「指揮命令下の労働」であると認定しました。その上で、労働基準法34条が定める休憩時間が確保されていなかったことを違法と判断したのです。
この判決は、たとえ給特法が存在しても、教員の全ての業務がその適用対象となるわけではないことを司法が明確に認めた点で、これまでの給特法の解釈に一石を投じるものとなりました。これまで「自主性」の名の下に曖昧にされてきた校外活動など、具体的な指揮命令が伴う業務について、今後は労働基準法に基づいた権利を主張できる可能性が出てきました。教員の長時間労働是正に向けた、大きな一歩となる判例です。
参考「判決文 2021年10月1日 さいたま地裁」(埼玉教員超勤訴訟・田中まさおのサイト,2025年7月15日参照)より
参考「「ブラック教職」是正の突破口か 公立教員の残業で賠償命令、労働弁護士はどう見る」(弁護士ドットコムニュース,2025年7月16日公開,2025年7月17日参照)より
参考「画期的?公立教員の長時間労働に「一石投じる判決」、浮き彫りになる給特法の矛盾」(東洋経済新報,2025年7月6日公開,2025年7月15日参照)より
「心の病」や「過労死」の一因にも
長年、「自主性」「自発性」が強調され、長時間勤務が常態化してきた教育現場では、教員の心身が蝕まれる深刻な事態が進行しています。その最も顕著なデータが、精神疾患による休職者の増加です。
文部科学省の最新調査によると、2023年度に精神疾患によって休職した公立学校の教職員数は 7,119人 に上り、 3年連続で過去最多を更新しました。在職者全体に占める割合も0.77%に達し、民間企業の平均(0.4%)を大きく上回っています。特に、経験の浅い20代、30代の若手教員の休職が目立っており、未来を担う人材が疲弊し、教壇を去らざるを得ない状況が深刻化しています。
| 年度 | 精神疾患による休職者数 | 在職者に占める割合 |
|---|---|---|
| 2019 | 5,478人 | 0.59% |
| 2020 | 5,203人 | 0.57% |
| 2021 | 5,897人 | 0.64% |
| 2022 | 6,539人 | 0.71% |
| 2023 | 7,119人 | 0.77% |
悲しいことですが、過労死に至る教員が多いことにも目を向けなければなりません。毎日新聞が2018年に調べたところ、2016年度までの10年間で過労死した公立学校の教職員は63人に上りました。過労から自殺に至るケースも多く、近年、過労が原因で自殺した教員の遺族が、自治体などに損害賠償を求める行政訴訟が相次いでいます。最近では2017年に自殺した茨城県古河市の遺族が「自殺は長時間労働や連続勤務に対して学校長が安全配慮義務に違反したことが原因」として水戸地裁下妻支部に提訴し、2025年1月、市が7000万円の賠償金を支払うことで和解しています。
引用・参考「令和5年度 公立学校教職員の人事行政状況調査について(概要)」(文科省,2025年7月15日参照)より
参考「公立校、10年で63人 専門家『氷山の一角』」(毎日新聞,2018年4月21日公開,2022年7月27日参照 ※現在非公開)より
参考「月120時間超残業の教諭自殺 地裁、県と町に賠償命令」(朝日新聞デジタル,2019年7月10日公開,2022年7月27日参照)より
最新の動向・議論
2025年給特法改正とその内容
教員の働き方を巡る状況を受け、国もついに抜本的な制度改正に向けて大きく動き出しました。2024年8月の中央教育審議会の答申を受け、政府が国会に提出していた改正法案が、2025年6月11日に可決・成立したのです。
改正法が掲げた改革の柱は、 ①教師の処遇改善、②学校における働き方改革の一層の促進、③学校の指導・運営体制の充実 を「三位一体」で進めるというものです。
教師の処遇改善
最大の焦点である①の教師の処遇改善では、教職調整額が給料月額の4%から10%まで段階的に引き上げられることが決まりました。時間外勤務手当の代替として長年据え置かれてきた額が、教員の高度専門職としての責務に見合う水準へと見直されます(ただし幼稚園教諭はすでに処遇改善が行われているため対象外)。また、校務の内容に応じて「義務教育等教員特別手当」を支給する仕組みが整備され、学級担任など困難性の高い業務には加算が想定されています。あわせて、指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しないことも新たに規定されました。
学校における働き方改革
②の「働き方改革の一層の促進」については、国・地方教育委員会・各学校の三者に義務や必要な措置が明示されています。
まず国に対して、教職員の業務量の管理や健康確保措置の実施に関する基本的な方針を定めるとともに、地方自治体や学校の取り組みを支援する責務が明記されました。その中には、勤務終了から翌日の始業までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」の導入や定着に向けた必要な支援も含まれており、学校現場での具体的な取り組みが促進されることが期待されています。
次に、地方教育委員会には、各地域における教職員の勤務実態や業務の状況を把握し、それに基づいて業務量管理や健康確保措置を講じる「実施計画」を策定し、公表することが新たに義務付けられました。
そして、学校(管理職)には、日々のマネジメントの中で勤務時間の把握や業務配分の見直し、教職員の心身の健康に配慮した職場環境の整備などを通じて、業務の適正化と負担軽減を実現することが求められています。
学校の指導・運営体制の充実
③の学校の指導・運営体制の充実では、まず校内マネジメント強化のため、「主務教諭」の職が法令上位置づけられました。主務教諭は学校の教育活動に関して教職員間の総合的な調整を行う職で、2008年に設置された「主幹教諭」「指導教諭」とは別の職となります。
また、公立中学校における2026年度からの35人学級の実現が明記され、少人数教育の推進が行われます。さらに、スクールカウンセラーや学校運営協議会委員といった外部人材との連携を強化することも盛り込まれており、多様な専門性を活かした協働体制の構築が進められます。文科省は、これらの施策を通じて、「組織的な学校運営及び指導の促進」に繋がるとしています。
- 教師の処遇改善
- 教職調整額を給料月額の4%から10%まで段階的に引き上げ
- 学級担任等への手当を支給
- 学校における働き方改革の一層の促進:
- [国]業務量管理・健康確保措置に関する方針の策定と支援の責務を明記
- [国]勤務間インターバル導入・定着への支援
- [地方教育委員会]業務量管理や健康確保措置についての「実施計画」の策定・公表を義務付け
- [各学校]勤務時間管理・業務見直し・健康配慮が求められる
- 学校の指導・運営体制の充実:
- 主幹教諭等の中核的役職による校内マネジメントの強化
- 公立学校における35人学級の実現
- スクールカウンセラーや学校運営協議会委員など外部人材との連携強化
参考・引用「「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議において可決され、成立しました」(文科省,2025年6月11日公開,2025年7月18日参照)より
参考「教師を取り巻く環境整備について(学校における働き方改革、指導・運営体制の充実、教師の処遇改善)」(文科省,20025年7月18日参照)より
改正内容への批判と課題
「教員の働き方改革」は進むのか
上記のように改正された給特法ですが、この中の「教職調整額の10%への引き上げ」という決定に対しては、教育現場や専門家から強い懸念や批判の声が上がっています。日本教職員組合(日教組)や日本弁護士連合会(日弁連)などは、一貫してその問題点を指摘しています。
その批判の主張の核心は、「教職調整額をいくら引き上げても、残業代が支払われない限りいわゆる“定額働かせ放題”の構造は温存される」という点です。たとえば日弁連は「給特法の廃止を含む抜本的な見直し」を求めており、「調整額の引き上げは、むしろ長時間労働を追認し、固定化させる危険性がある」と警鐘を鳴らしています。
ただ、一方で「給特法の完全廃止にも慎重になるべきだ」と主張する声も挙がっています。教育研究家の妹尾昌俊さんは、労働基準法の完全適用によって、校長や教頭が教員の業務内容や時間の使い方にこれまで以上に細かく介入するようになる可能性を指摘しています。たとえば、「なぜそんなに時間がかかるのか」「その業務は必要なのか」といった問いかけが増え、教員の創意工夫や学級ごとの柔軟な対応が制限されるおそれがあると述べています。実際、働き方改革の中で「学級通信を全校でやめる」といった事例が多くあがっており、教員に裁量があることで実施されていた数々の取り組みが縮小してしまうのではないかと危惧しています。
学校現場では、児童生徒の多様な状況に応じた対応が求められるため、教員の裁量が重要です。妹尾さんは、教員の創意工夫や主体性を尊重しながら、過剰な管理に陥らないような制度設計について熟議するべきだと述べています。
参考「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の成立に対する書記長談話」(日本教職員組合, 2025年5月23日公開, 2025年7月17日参照)より
参考「教員の働き方に関する給特法の見直しについての会長声明」(日本弁護士連合会, 2024年2月1日公開, 2025年7月17日参照)より
参考「先生たちの残業は減るのか?給特法改正が衆院通過、修正案でも積み残された5つの課題」(東洋経済新報社,2025年5月22日公開,2025年7月24日参照)より
教員の労働時間把握は本当に不可能?
「教職調整額の増額ではなく残業代を支払う方法で対処すべき」という主張に対し、文部科学省や一部の政党は、「教員の仕事は創造的な側面が強く、どこまでが労働時間か明確に線引きできない」という立場をとっています。これは給特法が出来た際の考え方を踏襲したものであり、教員の自主性・創造性を守ることを重視しているとも言えます。
一方で、以前は公立と同様に残業代が出ない仕組みが採用されていた私立学校や国立学校(国立大学の附属学校など)の教職員は、既に労働基準法に基づき労働時間が管理され、時間外労働には残業代が支払われるようになっています。つまり現状は、公立学校の教員だけが「時間の把握ができない」ということになっており、その矛盾を指摘する声もあります。
また、労働安全衛生法において、業種を問わず全ての事業者(管理者)に労働者の労働時間を客観的な方法で把握する義務を課している点が挙げられます。労働時間把握の対象には裁量労働制が適用されている労働者も含まれており、「把握できない」という主張自体が、管理者の責務を放棄しているとの指摘もあります。文科省が2012年に発行した冊子にも「学校においても「労働安全衛生法」に基づき労働安全衛生管理体制の整備が求められています」と明記されており、それに照らすと、公立学校にも労働時間把握の義務があるのでは?という疑問も湧いてきます。
引用「学校における労働安全衛生管理体制の整備のために」(文科省,2012年3月,2025年7月17日参照)
歪められる勤務時間
給特法改正によって「働き方改革の一層の促進」が掲げられ、勤務時間の適正な管理が求められる一方で、その実態が現場で歪められているという問題も浮上しています。神戸新聞の報道によると、兵庫県内の複数の中学教諭が、「過労死ライン」とされる月80時間を超える残業の記録を付けた際、管理職から過少に報告するよう指導を受けていたことが判明したのです。
これは、「学校における働き方改革の一層の促進」の根拠となるはずの労働時間が、上司からの圧力で事実とは異なる報告がされていることを示しています。このような不適切な労働時間管理は、教員の過酷な労働実態を隠蔽し、真の問題解決を阻害するものです。現場の長時間労働が続き、その実態が隠され続ける危険性があると言えるでしょう。
参考「教諭の残業時間、80時間より過少報告するよう指導 管理職が「過労死ライン」意識 兵庫で複数判明」(神戸新聞,2025年3月31日公開,2025年7月17日参照)
現場の教員にできること
法改正や地裁判決など、教員の労働環境の改善に向けた動きが少しずつ進んでいます。それでは、今まさに給特法のもとで日々働いている教員は、更なる改善のために何をすればよいでしょうか。
何より大切なのは、教育現場の実態を広く世論に伝えるため、まずは労働記録を付け、客観的なデータを残しておくことです。始業・終業時刻、休憩時間、行った業務内容などを日々記録することが、自らの労働実態を証明する最も強力な武器となります。
前述の「さいたま地裁判決」で、裁判官が「給特法は実情に合わない」という踏み込んだ付言をした背景には、原告の教員が毎日克明に勤務記録を付け、裁判資料として提出していたことが大きく影響しています。客観的なデータがあったからこそ、裁判所は過酷な労働環境を具体的に把握し、制度の問題点を指摘できたのです。
そして、改善のために声を上げ続けることも重要です。School Voice Project では、WEBアンケートサイト「フキダシ」で、学校現場で働く皆さんから様々な意見を募り、まとめたデータをサイト上で公開しています。活発な議論から社会に新たなうねりを生み出すべく、ぜひ皆さんのご協力をお願いいたします。
引用「さいたま地裁令和3年10月1日判決」(埼玉教員超勤訴訟・田中まさおのサイト,2022年7月24日参照)より
まとめ
今なお公立学校教員に残業代が支給されない現状は、1971年に制定された「給特法」に法的根拠があります。この法律は、月の平均残業が8時間程度だった1966年の実態調査に基づき、給料月額の4%を「教職調整額」として支給する代わりに時間外勤務手当を支払わないと定めたものです。
しかし、制定から半世紀以上が経過した現在、教員の労働環境は激変しました。2022年度の調査では、教員の時間外勤務は「過労死ライン」とされる「月80時間」を超える教員が小学校で14.2%、中学校で36.6%存在するなど、給特法は時代の実情にそぐわないものとなっています。その結果、精神疾患による休職者数は過去最多を更新し続け(2023年度で7,119人)、教員志望者の減少などの深刻な人材不足も引き起こしています。
この危機に対し、司法は「給特法は実情に合わない」(さいたま地裁)と警鐘を鳴らし、休憩時間不付与を労基法違反と認める(高松地裁)など、変化の兆しを見せています。そして2025年6月、政府は教職調整額を段階的に10%まで引き上げる改正給特法を成立させました。
しかし、この改正は「“定額働かせ放題”の容認だ」と各所から強い批判が出ています。この間の議論は、給特法の本来の目的である教員の自主性・創造性の尊重と、近年過酷化している教員の労働環境の改善の間での揺らぎとも言えます。どちらをより優先するべきなのか、またはどちらも守れるような新たな制度設計は可能なのか。日本の学校教育は今、大きな岐路に立っていると言えるでしょう。
今回の法改正は「結果」ではなく「過程」です。教員の働き方の問題を解決していくためにはこの法改正もテコにしながら、むしろここから様々な施策を推進していくことが必要でしょう。School Voice Project は、今後も「教員不足をなくそう緊急アクション」などを通して、政治や行政の場への働きかけを続けています。
学校現場をより良くするためには、現場から声を上げ続ける必要があります。School Voice ProjectのWEBアンケートサイト「フキダシ」の活用などを通じ、力を合わせて日本の教育を明るくしていきましょう。
《教職員WEBアンケートサイトはこちら》
同じカテゴリの記事
学校教育の知識を増やす

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-
久保拓