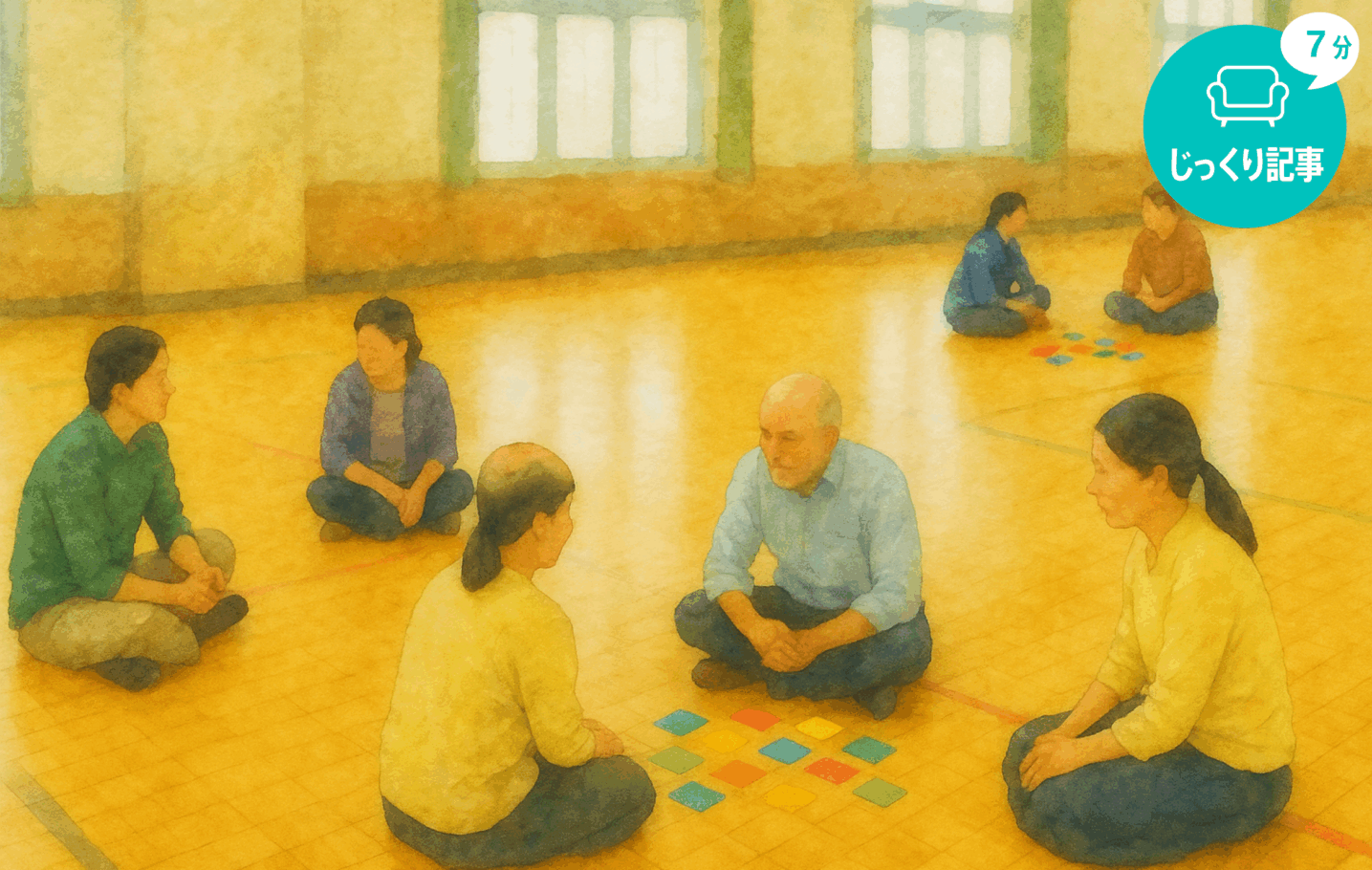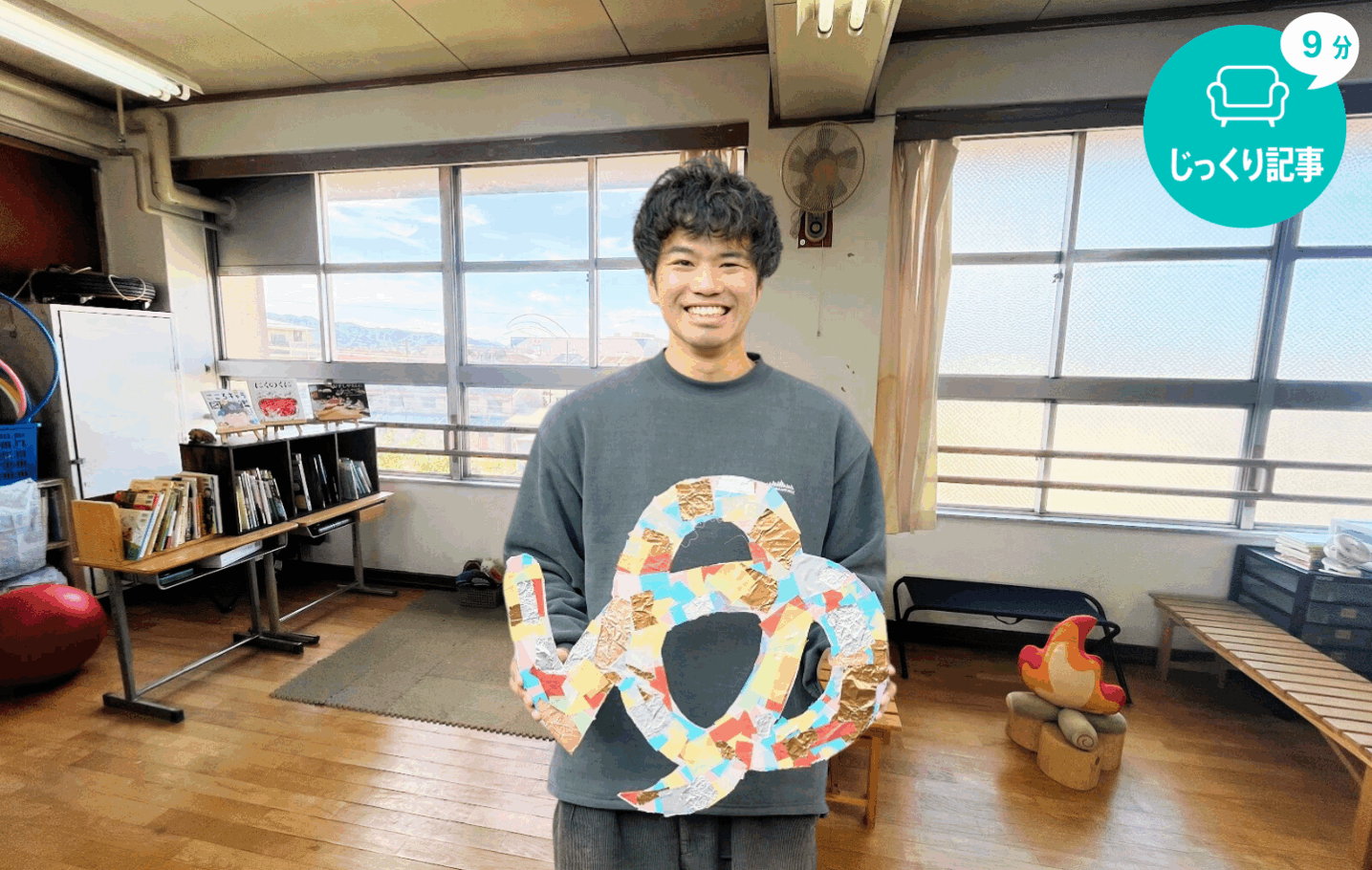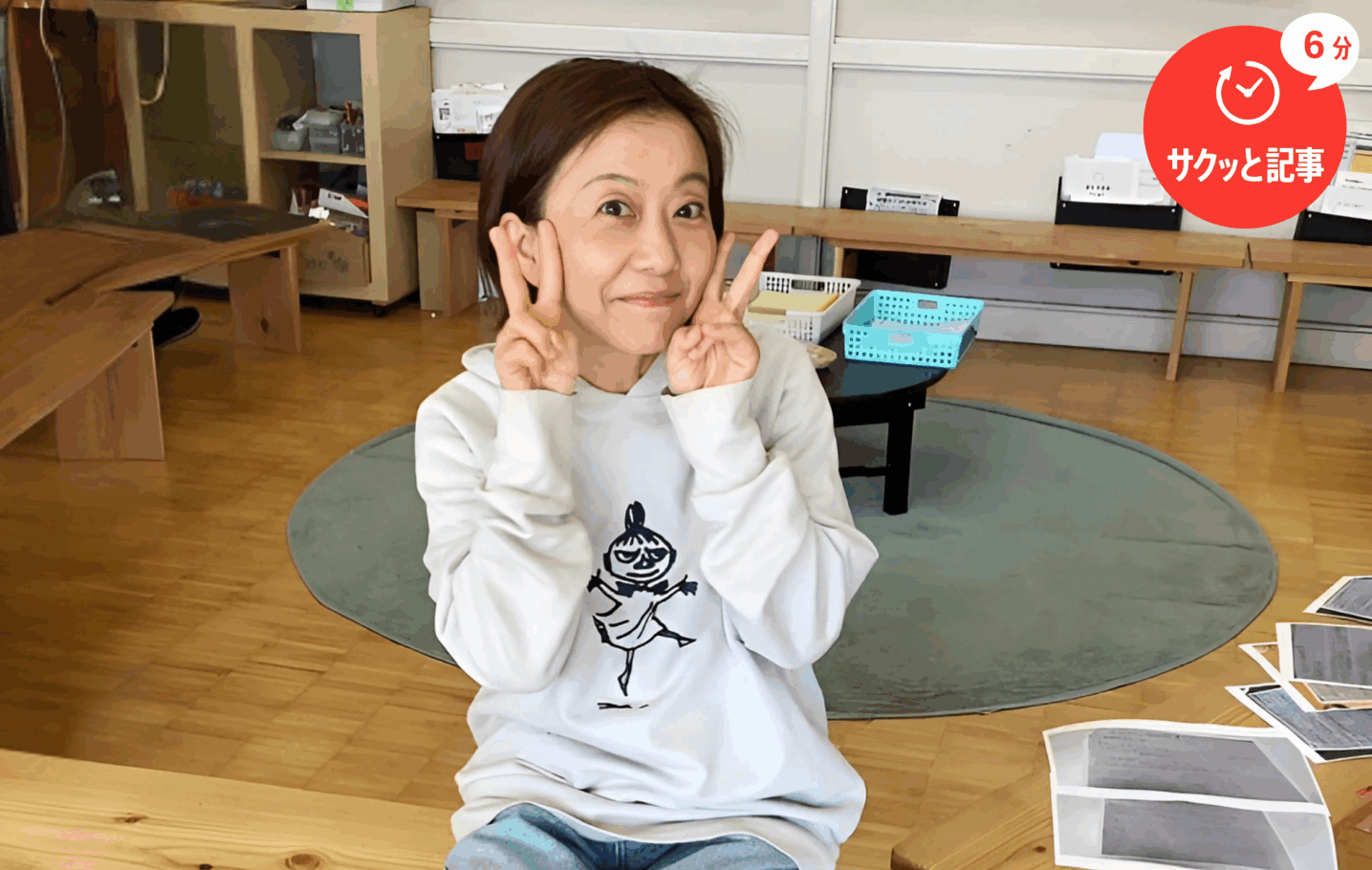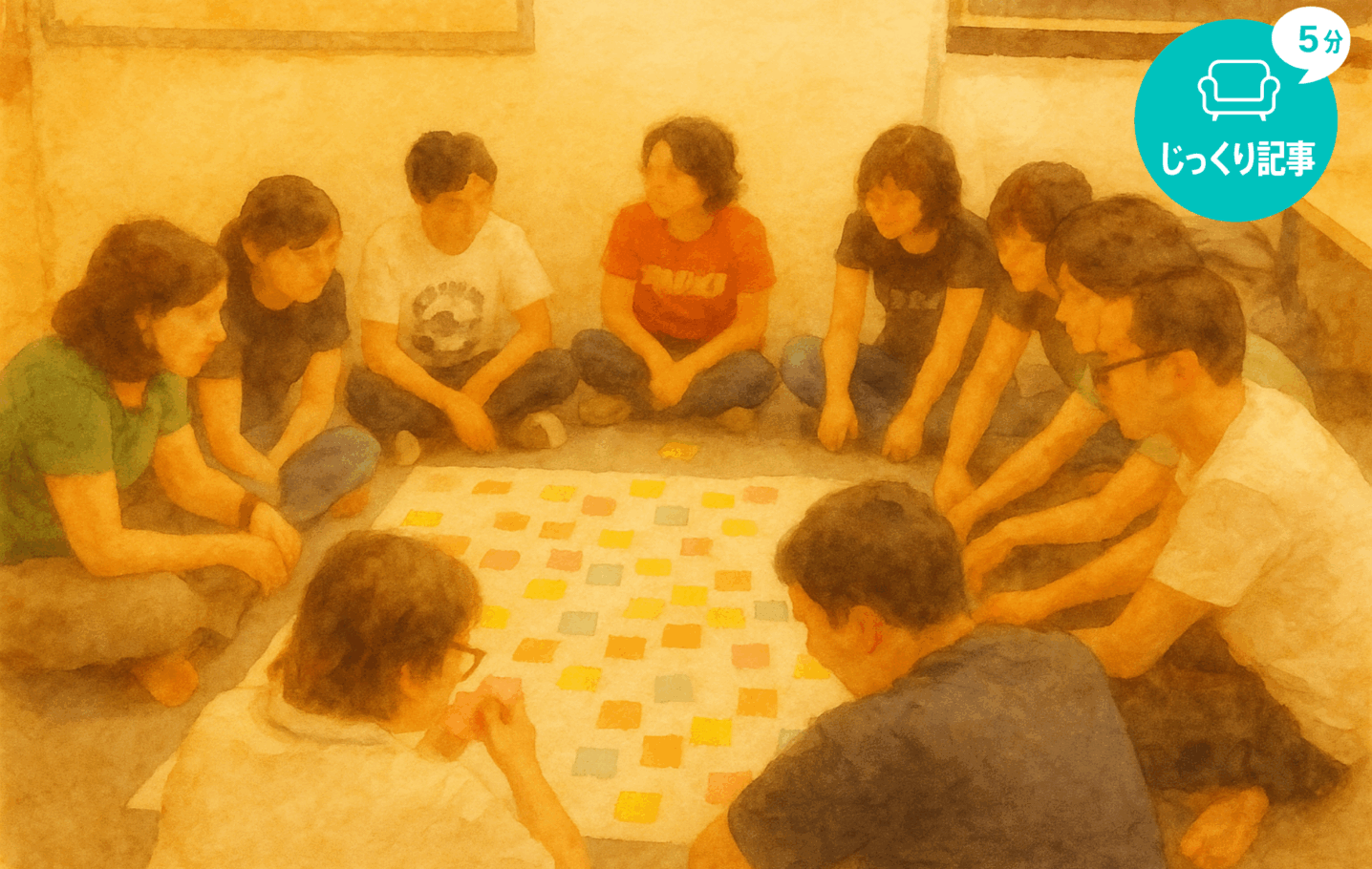
【後編】「プロジェクト型研究」で広がる、先生たちの学び合い。沖縄の小学校で生まれた校内研修
沖縄県うるま市の公立小学校に勤める親田拓之さんは、2024年度から校内研修(副)主任として、教員が主体的に学び合える仕組みづくりに取り組んできました。
前編では、「嘆きの共有の場」や「人生の道」といった取り組みを通じて、教員同士の関係を深めていくプロセスを紹介しました。後編では、そこで生まれたつながりが校内研修にどう活かされているのか、具体的な実践に焦点を当てていきます。
先生それぞれの「やりたい」から始まるプロジェクト型研究
——— もう一つの取り組みである「プロジェクト型研究」は、どのように生まれたのでしょうか?
「人生の道」や「嘆きの共有の場」などの対話の場をつくっていく中で、「私はもっとこんなことがやりたい」という声が出てきたんです。ただ、先生によって大事にしていることや関心はそれぞれ違いますよね。なので、ニーズを汲み取って、「自分の関心ごとを中心に学び合う『プロジェクト型探究』として取り組んでみませんか?」と提案したのが始まりです。
——— なるほど。ここでも先生方の思いを出発点にしたわけですね。どのように探究するテーマを決めていったのでしょうか?
それぞれの先生方がテーマを選ぶまでのプロセスは、丁寧に行っていきました。まずはアンケートを取って先生方の関心をリサーチし、そこから十数のテーマに整理しました。その後、先生一人ひとりが興味のあるテーマを3つ選び、その理由ややりたいことを書いてもらいます。さらに、ワールド・カフェのように同じテーマを選んだ人同士で模造紙を囲み、思いを聴き合う時間もつくりました。そのようなプロセスを経て、最終的に自身が探究するテーマを決めてもらいました。
今年度(2025年度)から、特別支援や哲学対話、自由進度学習、異学年交流、ICT、道徳など、それぞれが自分の関心のあるチームに所属して活動しています。
※ワールド・カフェ:カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、参加者が少人数のテーブルで自由に意見交換を行い、定期的にメンバーをシャッフルしながら対話を深める話し合いの手法
——— 具体的に、どのようなことをするのでしょうか?
私が所属している「哲学対話チーム」では、ある先生がふと「幸せって何ですかね?」と問いかけたことをきっかけにみんなで語り合ったり、また別の先生が「『嫌われる勇気』という本がすごく良かった」と話してくれたことをきっかけに、皆で読んで感想をシェアしたりもしました。こうした時間は、これまでの学校にあった「当たり前」を問い直すきっかけになっています。
また、「異学年交流チーム」では、学年の違う6クラスで縦割りグループをつくって活動する実践をしています。まずは、カードゲームやボードゲームなどで遊び、子どもたち同士の関係づくりから始めていました。そして、関係性が出来てきた頃に、算数を一緒に学ぶ時間もつくろうと試みています。「特別支援チーム」では、子どもたちの自立活動を充実させるために個別の支援計画を丁寧に作ったり、講師の方を学校に招いて新たな領域を学び、実践したりもしています。
活動の頻度は月1回のチームもあれば月2回集まるチームもあり、それぞれに委ねています。やりたい思いを持っている先生が中心となって進めているので、自然と学び合いが広がっていますね。
7月には各チームごとに中間発表をしたのですが、もう本当に感動しました。正直、最初はどこまでかたちになるか不安だったんです。でも、実際はそんな不安が無駄だったと思えるくらい、価値のある時間になりました。どこも発表時間として決まっている10分を超えてしまうほど熱がこもっていて、私が「時間です!」と止めなければいけなくて(笑)。これまでの「与えられたものをやるだけ」の校内研修とはまったく違って、先生たちが主体的に動いている姿にワクワクしましたね。
——— すごい変化ですね。
そうなんです。ある先生は、他の業務との兼ね合いもあって忙しい時期に、「正直、追い込まれています!笑」と困りながらも笑顔で言ってくれる場面もありました。それを聞いた周囲の人が、「そうだよね。頑張ろう!」と共感したり励ましあったりする姿もあって。もちろん、一人ひとり大変さやモチベーションは違うと思いますが、そんな風に、自然と自身の状態を共有する空気が生まれてきたと思っています。
ただ、今年度(2025年度)から新しく赴任された校長に校内研修の取り組みを伝えたときには、正直あまり良い反応ではなかったんです。せっかく前向きな雰囲気ができてきたのに、またゼロからやり直さないといけないかもしれない――4月は、そんな不安を抱えていました。
それが、7月の中間発表のあと、校長が「来年度の校内研修もこれでいこう!」と言ってくださったんです。「先生たちが主体的になると、こんなに変わるんだね」と。
「つながり」が先生を支える土台になる
——— 今後は、どのようなことに取り組んでいきたいですか?
そうですね。校長もこの研修を前向きにとらえてくださっているので、大枠は今年度と同じようなかたちになると思っています。
ただ、その前に必ずやりたいのは、今年度の振り返りです。「今年やってみてどうでしたか?」「次はどんなことをしてみたいですか?」と、一人ひとりの先生の声を丁寧に聞いていきたいですね。新しく赴任する先生も含めて、ちゃんとヒアリングをして、チームとして次の一歩を決めていく。「こちらが勝手に決める」のではなく、みんなでつくっていくことを大切にしたいと思っています。
——— 最後に、教職員の働く環境をよりよくしたいと思っている読者の方に、メッセージをいただけますか。
やはり大切なのは「つながり」だと思います。隣にいる先生同士が安心して、ありのままの自分でいられること。それが何よりも強い土台になります。大きなことを始めようとしなくてもいいんです。
まずできる一歩は、先生同士で自分の気持ちや体験を語り合える場をつくることだと思います。例えば、これまでの人生のアップダウンを振り返って共有したり、最近のしんどさやモヤモヤを「嘆き」として打ち明けたりする。そんな時間を意識的に設けるだけで、相手の背景が見えてきて、「この人も同じように悩んでいるんだ」と気づける。そこから自然と安心感や信頼関係が生まれてきます。
内容や方法は学校によって違っていいと思います。大切なのは、ただ安心して話せる時間を確保すること。その空気があるだけで、先生たちは前に進む力を取り戻していけると思っています。
同じカテゴリの記事
実践を知る|職場づくり・組織開発

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-
建石尚子