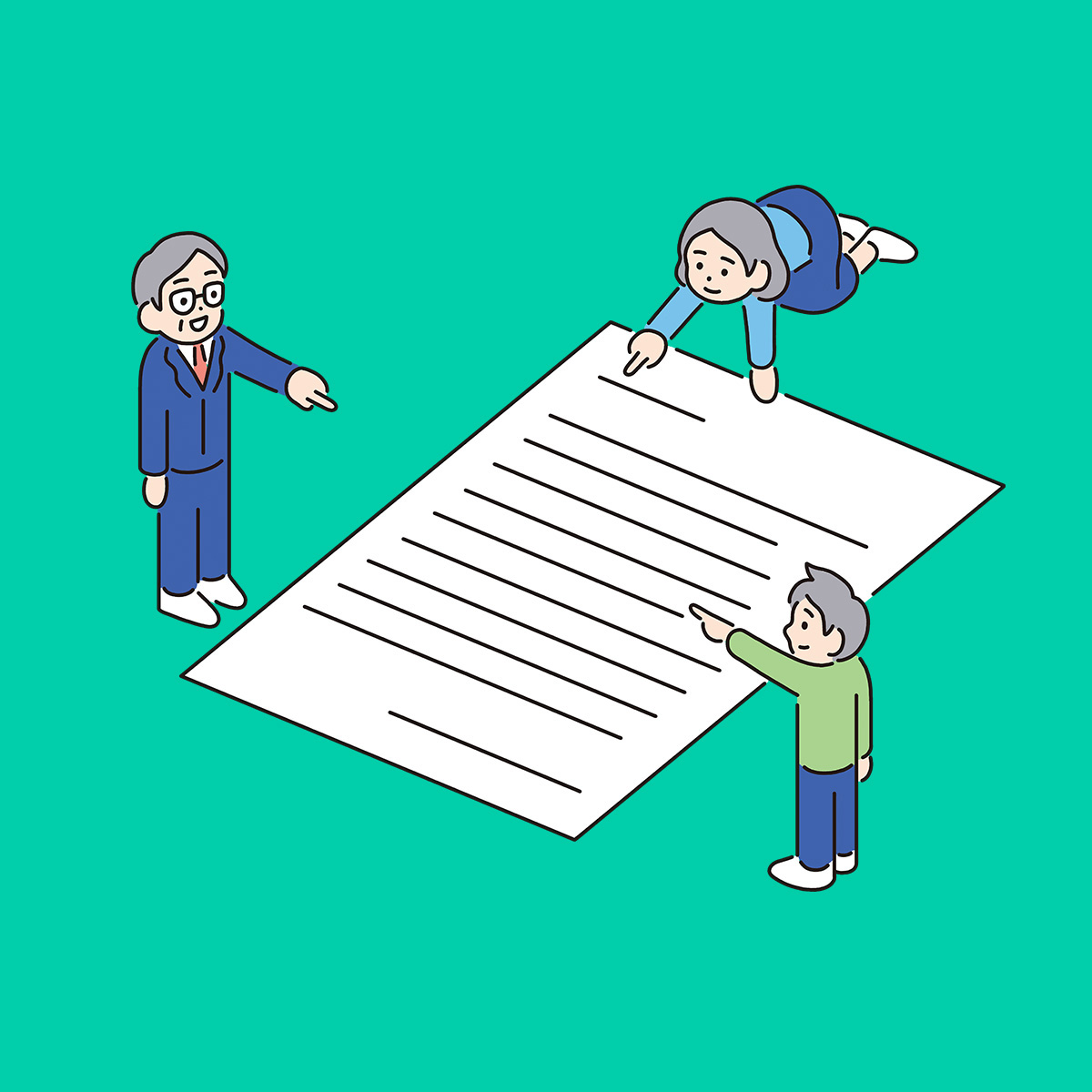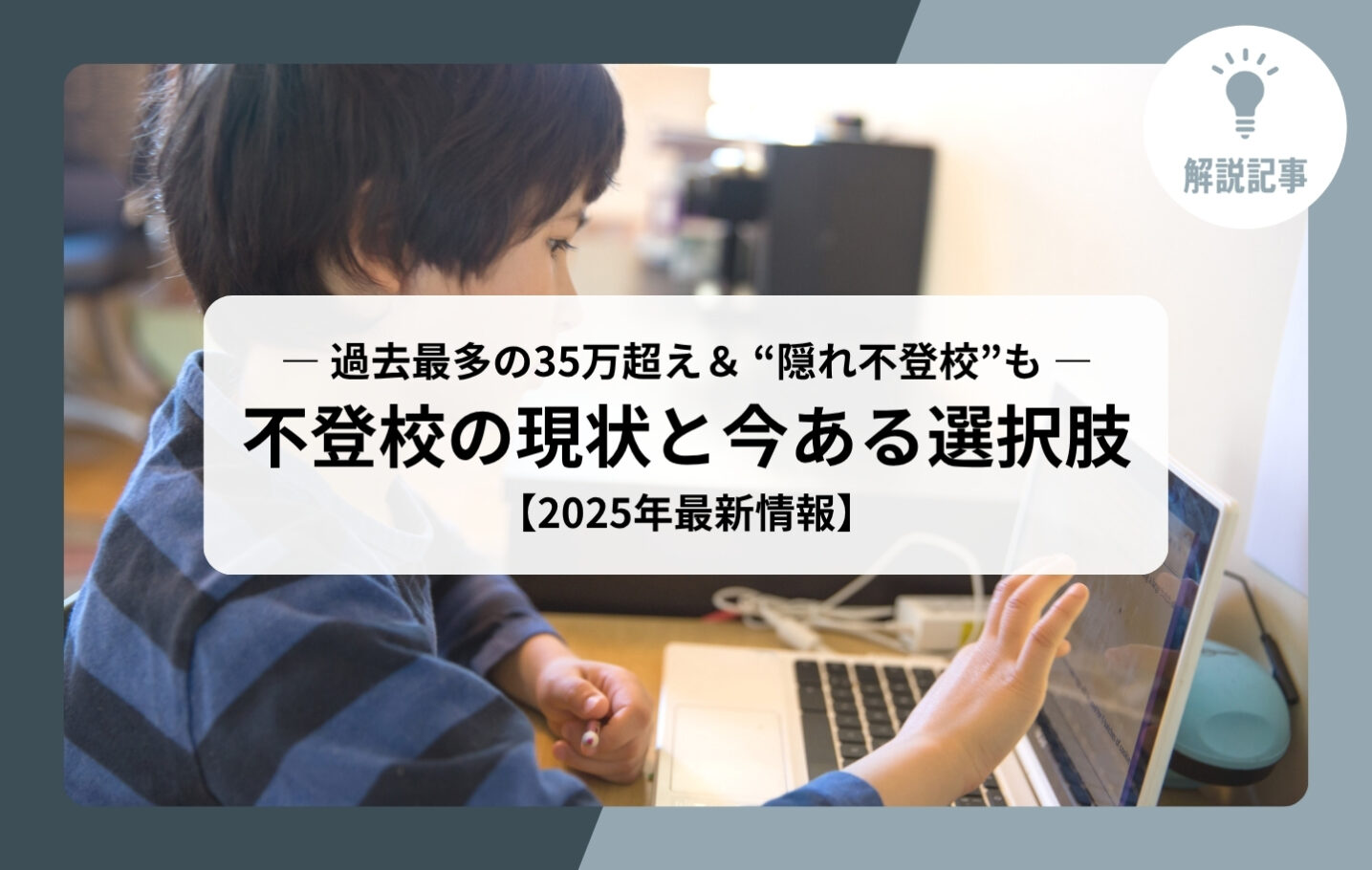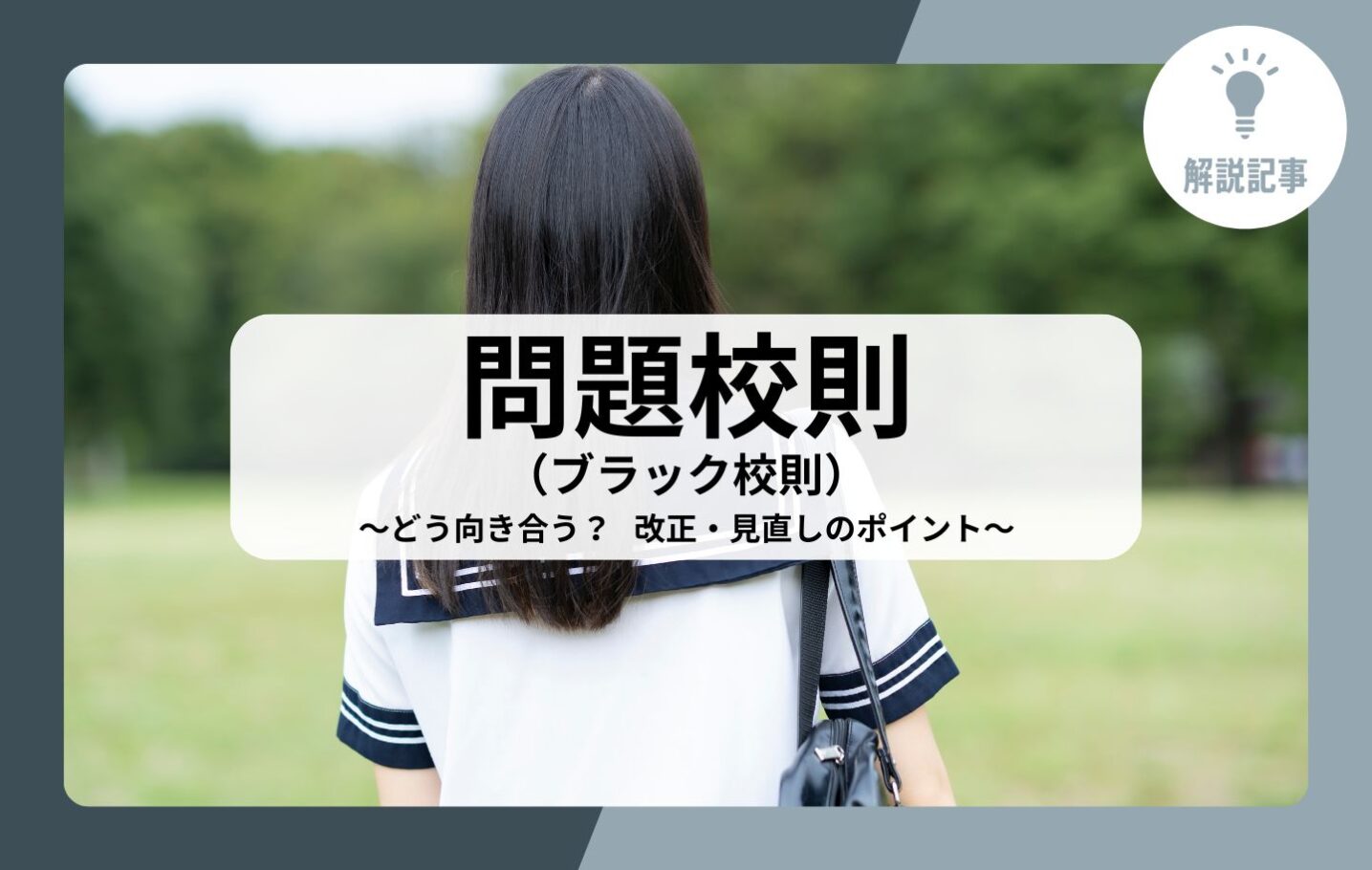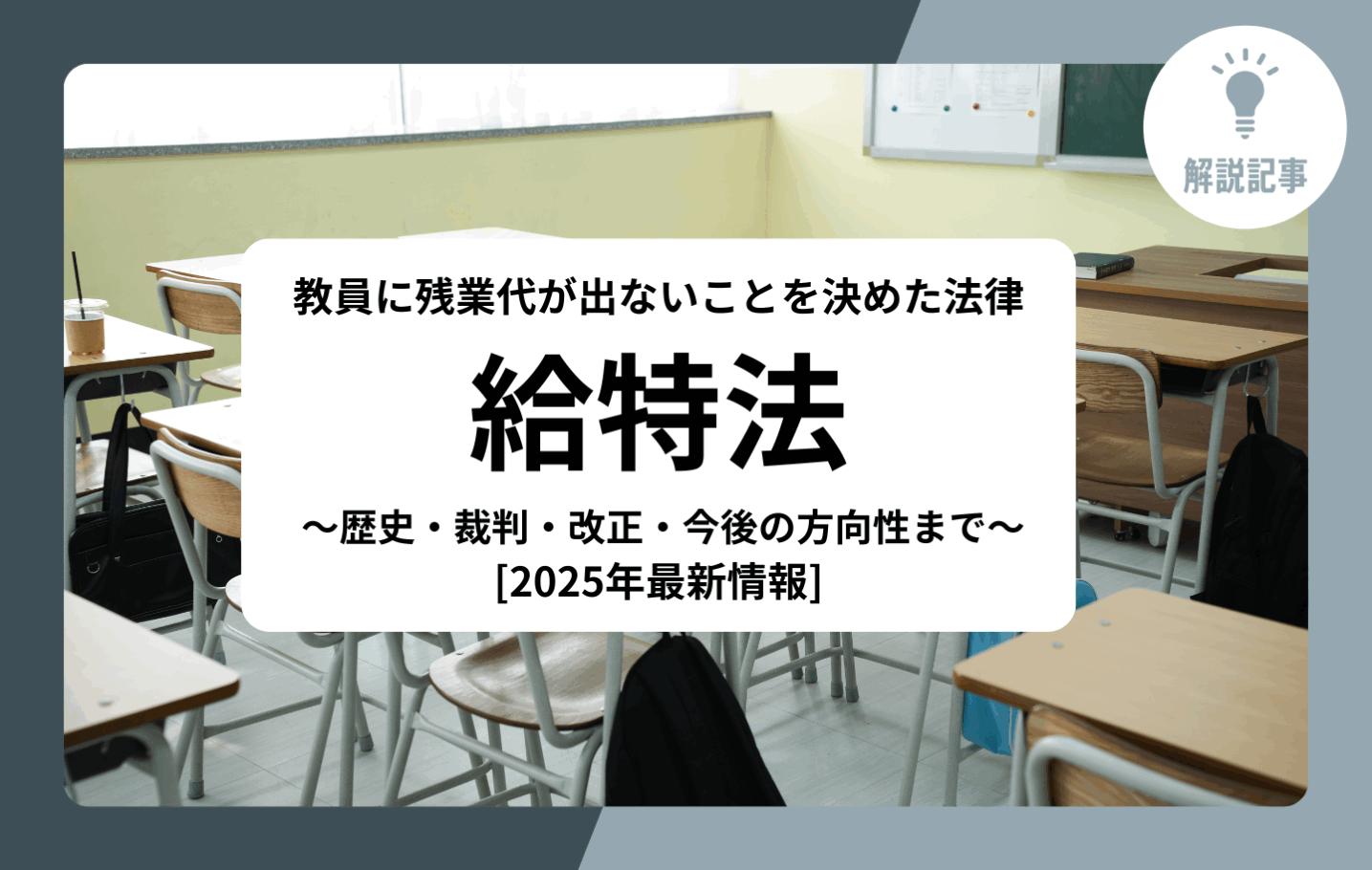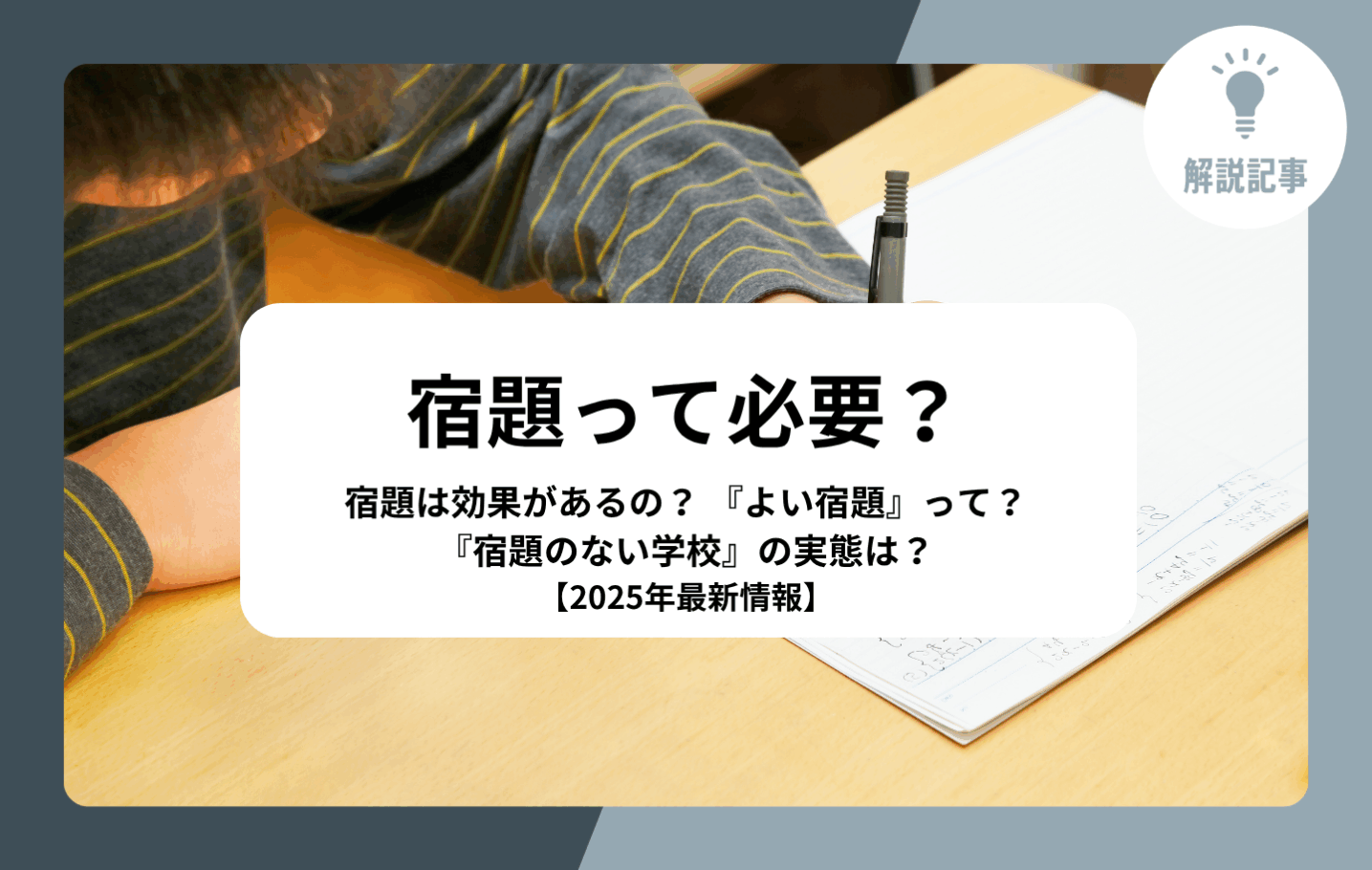
【解説記事】[2025年最新情報]宿題って必要? 論文・データでわかった宿題の効果とメリット・デメリット。「よい宿題」や「宿題のない学校」の実践例も紹介します
メディアでは、「宿題のない学校」や「宿題のない国」など、様々な教育が紹介されています。
それらの取り組みの根底にある教育観や、宿題の代わりに実施している取り組みなどについてまとめました。
「宿題のない学校」「宿題のない国」の教育観は?
宿題を出さないとしたら…? 宿題のない学校や国の取り組み
実際に宿題のない学校の事例3つと、海外の事例から、“なぜ宿題がないのか”、“その代わりにどのような取り組みをしているのか”を見てみましょう。
①「自由な子どもを育てる」きのくに子どもの村学園
最初に紹介する“宿題のない学校”は、きのくに子どもの村学園です。この学園は全国の5地域で計10校の小・中学校と1校の高等専修学校を運営しています。
学園では、「自由な子どもを育てる」という教育目標のもと、①自己決定、②個性化、③体験学習の3つの原則を掲げています。この原則は教師中心的・画一的・書物中心的な考え方の逆を目指すもの。それを具体化するように、学園の小・中学校にはテストや宿題がなく、〈プロジェクト〉と呼ばれる体験学習の場で学びを深めています。「その方針で教科学力はつくの?」という声も上がりそうですが、卒業生進学先では教科の成績も高い傾向にあるとのことです。
参考「宿題もテストもない!子供たちが自由な小学校とは?」(みんなの教育技術,2019年12月19日公開,2025年10月2日参照)より
参考「きのくに子どもの村学園」(きのくに子どもの村学園,2025年10月2日参照)より
②「ドリルを廃止」した茨城県水戸市立石川小学校
2校目は、宿題の中でもドリル宿題を撤廃した茨城県水戸市立石川小学校です。同校の豊田校長は①ドリルは効果が上がらない、②先生たちの負担が大きい、という現状を考え、家庭学習と教師の働き方の両方の改革としてドリルの廃止に踏み切りました。
ドリルの代わりの取り組みとして、同校では前項でも紹介した“家庭学習ノート”を取り入れています。そこには“やらされるのではなく自ら学ぶ習慣を身につけてほしい”という学校の想いがあり、保護者にアンケートを取るなどして、地域とも連携し改革を進めていきました。結果、子どもたちが生き生き家庭学習ノートに取り組むだけでなく、教員の時間外労働時間も月に10時間以上減少したそうです。
参考「ドリル宿題はもうやめます!“当たり前”を見直した水戸市立石川小学校の挑戦」(NPO法人 教員支援ネットワーク T-KNIT,2022年2月1日公開,2025年10月2日参照)より
③「自律した子どもを育成する」横浜創英中学・高等学校
次は、“宿題を全廃”している横浜創英中学・高等学校です。この学校の校長先生は、東京都の麹町中学校で数々の改革をしたことでも有名な工藤さん。
工藤校長は宿題などに多くの時間が奪われているのに学力が上がらない日本の教育スタイルに疑問を持ち、宿題のほか定期テストや担任制なども廃止しました。そのことを通じて、ただ与えられるだけの学習でない、今後社会で生きる力をつけるための”学び方の習得”を目指しています。その目標に従い、例えば数学では3年間一度も一斉授業を行わずに分からないことを調べ聞くという形式で授業を行っているそう。その結果、学習の遅い子でも通常授業を行う時間の半分で学習が終了するなど、自分で学ぶことの効率のよさが実証されているようです。
参考「宿題も定期テストも廃止!「当たり前」をやめた校長が考える「教育」のこれから」(WASEDA NEO,2020年10月2日公開,2025年10月2日参照)より
海外の事例
国全体で宿題が禁止となっていたり、「宿題のない学校」が増えている例もあります。
フランス
フランスでは1956年に小学校での筆記の宿題が禁止されました。そもそもの禁止理由は、
- 子どもの過労リスク回避
- 学校外で勉強をする際の環境が悪い
- 教師たちは添削よりも優先すべきものがある、
の3点でしたが、現在でもこの制度が続いている理由はフランス国内の教育格差が激しいことにあると言われています。フランスでは、家庭間の文化的・経済的なギャップや地域格差などから、恵まれた環境の子どもとそうでない子どもの不平等が深刻です。そのため、学習環境が整っている「学校での学習時間」、特に個別指導の時間を長くするべきであるという考えが強く、筆記宿題の禁止が続いています。
ただし、実際の運用では温度差があるとの報告もあります。公式な禁止規定にもかかわらず、簡単な筆記練習や宿題を出す教員も多く見られるなど、現場での徹底は限定的なようです。また、宿題禁止規定はあくまで小学校に限定され、中学校以上では宿題が一般的に認められています。さらに、禁止規定の効力が時代とともに薄まり、1995年の通達以降は「校内学習時間を確保し、宿題を学校内で処理する仕組みを整える」方針が採られてきたという指摘もあります。
また、この制度には批判もあります。宿題禁止による学力低下への懸念などを指摘する声もあがっているなど、制度の理念と現場とのギャップを巡る議論は現在も続いています。
参考「フランスでは「宿題」を出すことが禁じられている、その深すぎるワケ」(現代ビジネス,2020年3月1日公開,2025年10月2日参照)より
参考「French parents to boycott homework」(The Guardian,2012年5月26日公開,2025年10月2日参照)より
参考「Homework, a war that lasts」(world.edu,2021年9月30日公開,2025年10月2日参照)より
参考「How can you encourage your child to do homework independently?」(Soft Kids,2025年10月2日参照)より
中国
2021年、政府は「双減政策」を打ち出し、子どもの学習負担と学習塾の費用負担を軽減するため、宿題に厳しい制限を設けました。小学1・2年生は筆記宿題が禁止され、中学生でも宿題は90分以内で終えられる量に制限されています。この政策により、多くの子どもたちの宿題時間が実際に減少したと報告されています。
こうした「双減政策」が導入された背景には、中国における過度な受験競争と、家庭の経済的・精神的な負担の増大があります。大量の宿題や放課後の通塾は、子どもたちの睡眠不足や心身の健康問題を引き起こし、都市部を中心に学習塾費用が高額化していました。政府はこの状況を「教育の公平性を損なう」と判断し、学校教育の質を高めることで家庭学習に過度に依存しない仕組みを整えようとしています。
宿題を減らした代わりに、中国の小中学校では授業内の学習効率向上が強く求められています。具体的には、放課後に学校内で「課後服務(補習・自習時間)」を設ける仕組みが広がってるほか、教師に対しては「授業の質を高める工夫」を義務づけ、協働学習や探究活動を増やすなど、単なる詰め込みではない学習方法への転換が進められています。
もっとも、「双減政策」は賛否両論を呼んでおり、一部の保護者からは「学力低下につながるのではないか」という懸念も出されています。しかし政府は「家庭の負担軽減と教育の平等」を最優先に掲げ、今後も学校教育の質的改善とバランスを取りながら進めていく方針です。
参考「学習塾の設立を規制した中国、小中学校の宿題量も制限…狙いは「少子化対策」」(読売新聞,2021年7月26日公開,2025年10月2日参照)より
参考「中国「双減」政策の影響と保護者の反応」(井上快,甲南大学教職教育センター,2025年4月25日)より
参考「中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》」(中華人民共和国中央人民政府,2025年10月2日参照)より
参考「Surprise, Controversy, and the “Double Reduction Policy” in China」(International Education News,2021年11月3日公開,2025年10月2日参照)より
参考「落实“双减”政策加速推进教育现代化」(人民日報,2024年10月21日公開,2025年10月2日参照)より
オランダ
オランダの小学校でも、宿題はほとんど出されません。「子どもの教育に責任を持つのは学校である」という考え方が社会に根付いており、学習は学校で完結させるべきだと考えられています。家庭は、勉強ではなく家族との時間を過ごす大切な場所と位置づけられています。
ただし、これはオランダ政府が「宿題禁止」を制度として定めているわけではなく、世論としても一律に「宿題不要」が一般認識になっているわけではありません。むしろ、研究者や一部の教育関係者が「宿題は効果が限定的であり、不平等を助長する可能性がある」と指摘し、それを受けて一部の小学校が「宿題フリー」を取り入れている、というのが実態です。宿題を課す学校も存在し、学年が上がると算数ドリルや読書課題など軽めの宿題を出すケースも見られます。
その代わりに重視されているのが、学校内での集中学習や、子どもが自分でテーマを選ぶプロジェクト型学習・発表課題です。さらに「アゴラ型(Agora)」と呼ばれる新しいタイプの学校では、学年や時間割の制約をなくし、教師が「コーチ」として子どもの主体的学びを支える取り組みも行われています。
「宿題がない」のはオランダ全体の統一方針ではありませんが、一部の学校や教育実践には確かに見られる潮流であり、その背景には「学びを学校で完結させたい」「子どもの主体性を尊重したい」という教育観が反映されているのです。
参考「オランダの小学校、宿題事情。」(木村優里オフィシャルサイト,2023年1月27日公開,2025年10月2日参照)より
参考「Gaat je kind naar een huiswerkvrije school? Lees dan dit blog lezen」(Wijzer over de Bassisschool, 2025年10月2日参照)
参考「Homework in Netherlands | Primary schools」(Young Expat Services, 2023年11月16日公開, 2025年10月2日参照)
参考「Deze school heeft geen huiswerk, klassen of leraren」(Jeugdjournaal, 2023年10月30日公開, 2025年10月2日参照)
番外編:フィンランド
最後に、「自由で宿題やテストがない国」というイメージのフィンランドを紹介します。…ただ、このイメージは日本ではやや間違って伝わっているようで、実はフィンランドでも多くの学校に宿題やテストがあります。フィンランドでは各学校ごとの独自性が高いので、「宿題やテストがない」というイメージが強いのは、一部の事例を取り上げたメディアの影響があるようです。むしろフィンランドは諸外国に比べ学校での学習時間が短いため、少しの家庭学習は学習習慣と記憶の定着のために重要と考えられています。
参考「フィンランド教育のウソと本当?」(フィンランドの学校に行こう!,2019年7月2日公開,2025年10月2日参照)より
まとめ
多くの教職員や児童が疑問に思う宿題の必要性については、様々な研究によりその効果が証明されています。しかし宿題の効果を最大限にするためには、“宿題の目的”と“その目標達成のための出し方”を理解する必要があります。そして、“何のために”“どのように”をきちんと考え宿題を出した上で、適切なフィードバックをすることも重要です。宿題の出し方によっては様々なデメリット面をカバーし、メリットを多く残すことも可能です。
近年の研究や国内外の先進事例が示すのは、宿題のあり方が「一律・強制」から「個別・選択・主体性」へとシフトしているという事実です。もちろん、宿題には学習内容の定着や学習習慣の形成といった重要な役割がありますが、大切なのはその「目的」を常に問い直し、子ども一人ひとりにとって本当に価値のある形を模索し続けることです。
また、宿題を出さなくても日々の学習方法を工夫することで効率的に学べる事例も報告されています。宿題のあるなしに関わらず共通して大切にされているのは、“子どもが自分で考え、自ら学びたいと思えるような学習環境”を整えることでした。
この記事をきっかけに、“これからの宿題”について改めて考えてみてはいかがでしょうか。
同じカテゴリの記事
学校教育の知識を増やす

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?
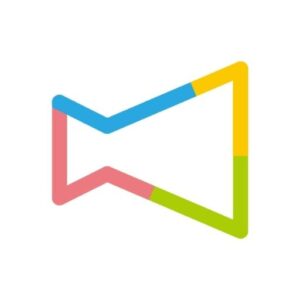
-
メガホン編集部